 しょんぼりねこ
しょんぼりねこ人生なんかどうでもいいです。特に楽しいこともない。
毎日辛いし疲れました・・・。
私には人生が行き詰まった時期があった。
22歳で大学を中退し、そのまま10年以上フリーターを続けた。27歳で始めた医学部再受験には失敗し、この先どうすればいいのか分からないまま、不安でいっぱいの日々を過ごしていた。
気づけばもう33歳。こんな経歴ではまともに仕事につくのも難しく、どうにもならない状況に追い込まれていた。まさに人生が完全に行き詰まっていた。
経歴は最悪、職歴なし、金なし、彼女なし、友達なし。まさに人生のどん底だった。
あわせて読みたい

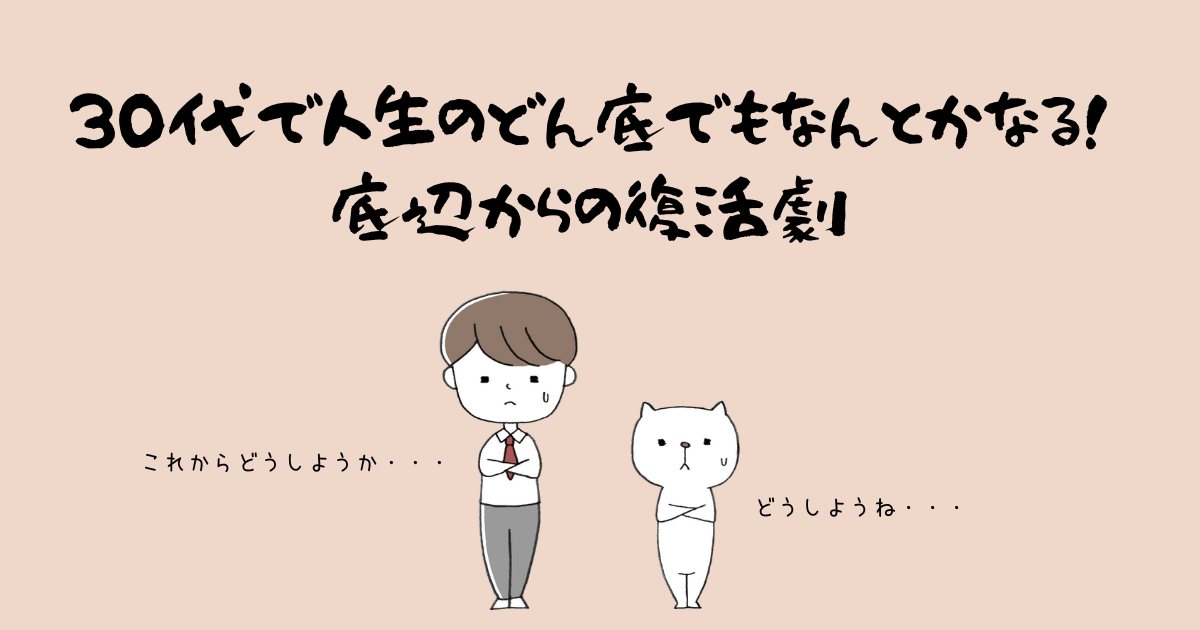
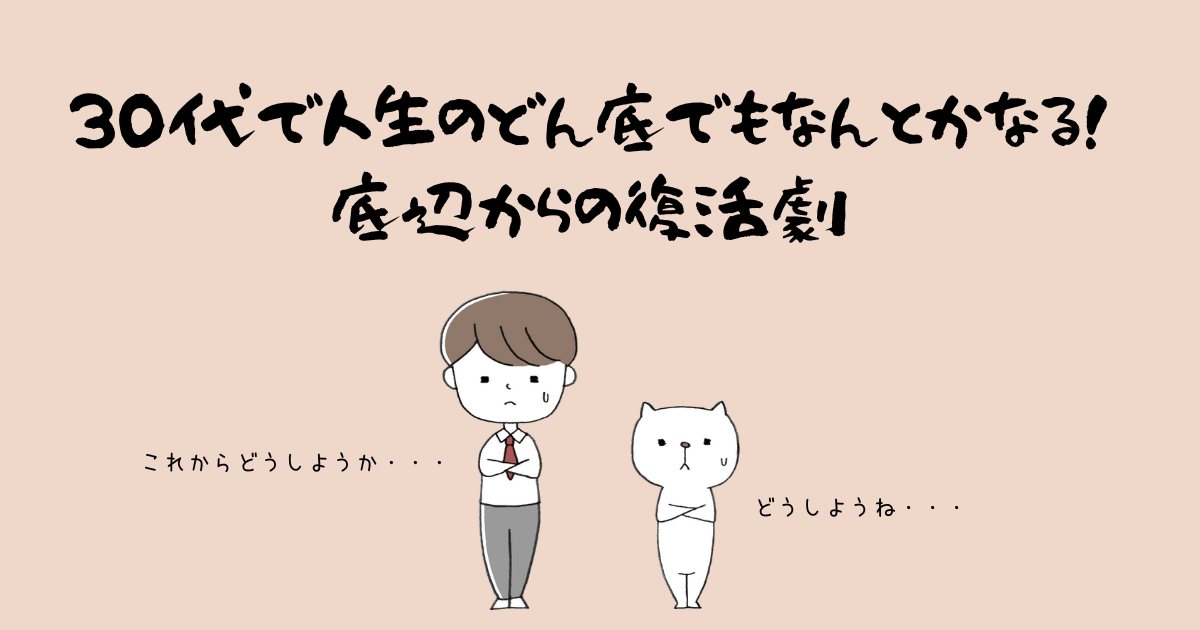
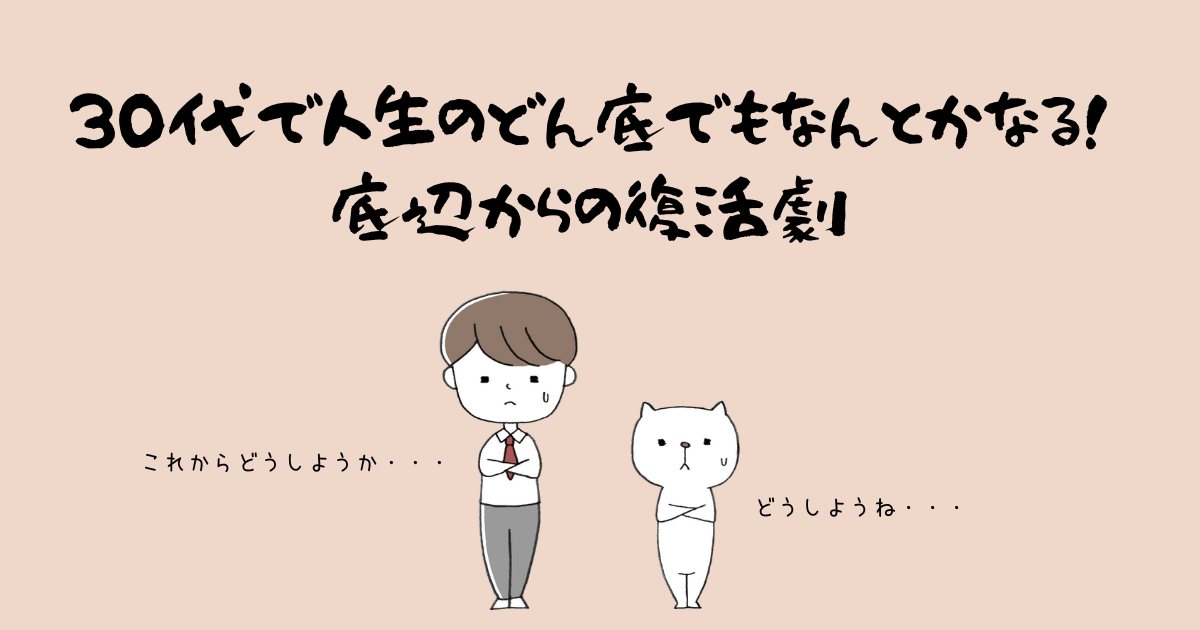
30代で人生のどん底でもなんとかなる!底辺からの復活劇
30代ですが人生のどん底です。どうしたらいいですか・・・。 人生でどん底を味わうことは何度かあるけれど、30代でどん底になると、取り返しのつかないこともある。人生…
私が人生に行き詰まった一番の原因は、仕事がなかったことだ。
ただ、人生が行き詰まる理由は人それぞれで、本当に千差万別だと思う。
その後、医者になる夢は諦めて、同じ医療職である理学療法士を目指すことにした。大学に入り直し、大卒の学歴と理学療法士の国家資格を取ったおかげで、なんとか37歳で初めて就職することができた。
しかし、せっかく就職した職場だったのに、人間関係のトラブルで揉めてしまい、ほとんど解雇のような形で退職することになった。
そして再び無職になり、今度は40代で人生が行き詰まってしまった。
もちろん、私の人生の行き詰まりはあくまで一例だ。
人それぞれに抱える悩みがあり、そのすべてを一つひとつ解決するのは難しい。
だからこそ、ここでは私が40代になってから人生の行き詰まりを解決するためにしたことを紹介したい。
結論から言えば、「いろいろやめてみること」で心の余裕を作ることだ。
そして一番いいのは、悩みの原因そのものをやめることだと思う。
とはいえ、もしその原因が仕事なら、簡単に辞めるわけにはいかない。
仕事を辞めるのは勇気がいるし、辞め癖がついてしまうと、私が言うのも申し訳ないが、どこに就職しても長続きしなくなる。だから正直おすすめはしない。
そもそも、いつも人間関係のトラブルで仕事を辞めてしまうタイプの人は、どんな職場に行っても人間関係でつまずく可能性が高い。
そうなると、解決策は「仕事を辞めること」ではなく、「人間関係の処世術を学ぶこと」になるだろう。
それなら、心の余裕を取り戻すために、心のリソースを消耗している他のことをやめてみるのがいい。
ここで紹介するのは、その中のほんの一部だけど、私が実際に試してみて心が軽くなった方法たちだ。
この記事は、わたなべぽんさんの『さらに、やめてみた。』をメインに色々な著書を参考にしている。
なお、私がフリーター時代にどうやって絶望から抜け出したのかを知りたい人は、下の記事を参考にしてほしい。
あわせて読みたい

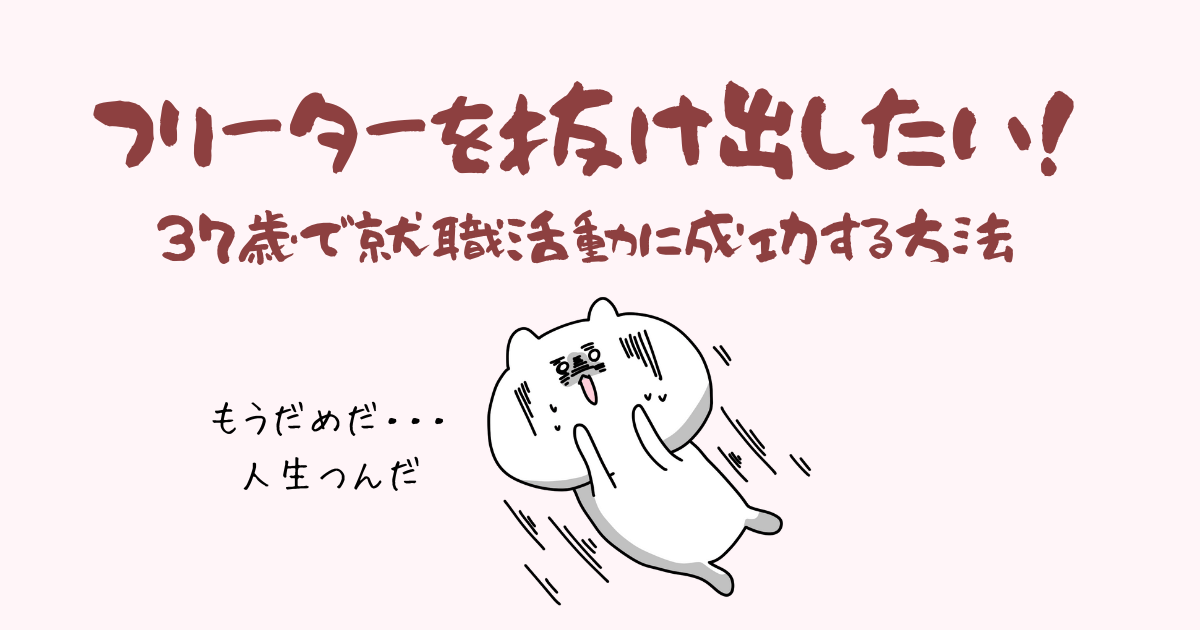
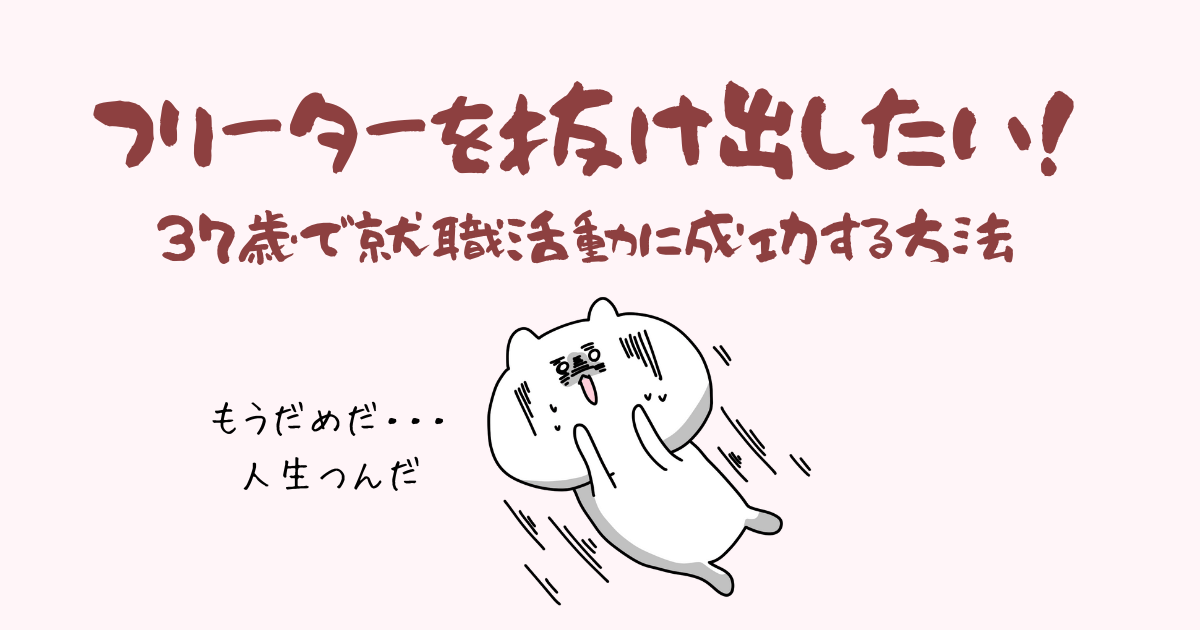
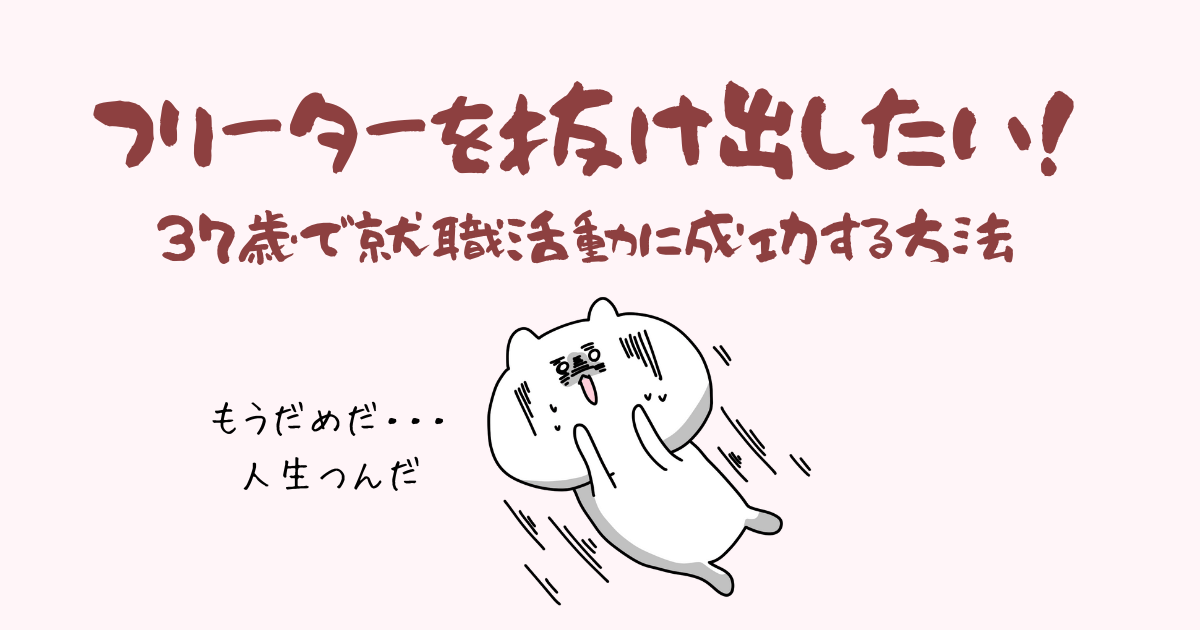
フリーターを抜け出したい!37歳で就職活動に成功する方法
ずっとフリーターをしていていますがフリーターを抜け出す方法が思いつきません。フリーターから抜け出す良い方法はありますか? フリーターを何年も続けると段々と就職…
リンク
目次
人生が行き詰った40代がやめてみるべきこと
察してほしい
人間関係で一番疲れるのは、やっぱり「気疲れ」だと思う。
職場でも家庭でも、無意識のうちに人に気を遣いすぎていないだろうか。
気を遣いすぎると、自分の気持ちを押し殺すことになる。
相手を思いやることは大事だけど、それが自分を苦しめる形になったら、本末転倒だ。
たとえば、体調が悪いときに「察してほしい」と思うことがある。
「こんなに具合悪そうにしてるのに、どうして気づかないの?」
「私はいつも察してるのに」と心の中で叫んでしまう。
でも、常に相手の心を読み取るなんて、無理な話だ。
気づけることもあれば、気づけないこともある。
それはお互い様。完璧に察し合える関係なんて、たぶん幻想だと思う。
わたなべぽんさん夫婦も、「察すること」ができなくてケンカしたそうだ。
旦那さんがきっぱり「察せません」と言い切ったエピソードがあって、妙にスッキリした。
そのくらい正直なほうが、むしろ人間らしいのかもしれない。
私は「察してほしい」と心の中でため込むよりも、ちゃんと口に出して伝えたほうがいいと思う。
気持ちは、言葉にしないと伝わらない。
それに、伝えたあとで分かり合えなくても、それはそれで仕方ない。少なくとも、自分の中にモヤモヤを残さずに済む。
世の中では「気遣いできる人=いい人」と言われがちだけど、私はそうは思わない。
気遣いができることよりも、自分を犠牲にせずに人と関われるほうがずっと大事だと思う。
私はもう、無理に気を遣わない。
わざわざ先読みも深読みもしない。
「何かしてあげたい」と思ったときだけ、素直に行動する。
そのほうが自然だし、疲れない。
別に誰かに好かれなくてもいい。
無理に合わせて生きるよりも、自分のペースを守れるほうが、ずっと幸せだ。
職場で気を遣いすぎて苦しくなっている人は、一度「気を遣うこと」をやめてみてほしい。
すぐにはうまくいかなくても、少しずつ自分の心が軽くなっていくはずだ。
一定の距離感を保って付き合うくらいが、ちょうどいい。
人は変えられない。どんなに頑張っても、相手が応えてくれるとは限らない。
だから、疲れる人とは距離を取り、割り切ること。
それが、自分を守る一番の方法だと思う。
人に気を遣いすぎるのは、もうやめよう。
自分を大切にできる人が、結局いちばんやさしい人なんだ。
時間厳守
時間を守ることは、社会人にとっては当たり前のことだ。
でも、自分がそう思っていても、時間を守れない人は一定数いる。
『元2ch管理人のひろゆき』も、「時間は守れない」と堂々と言っている。
つまり、世の中には「どうしても時間が守れないタイプの人」も存在するということだ。
「時間を守る・守らない」について話し合っても、結局あまり意味はないのかもしれない。
走るのが苦手な人、泳ぐのが苦手な人、数学が苦手な人がいるように、単純に“時間を守るのが苦手な人”もいる。
そう思うと、少し気が楽になる。
わたなべぽんさんは、そういう人と付き合うとき、「きっちり時間を決めて待ち合わせしない」という工夫をしている。
待つ前提で場所を決めたり、待ち時間をつぶせる工夫をしたりして、のんびり構える。
「相手が遅れるかもしれない」と分かったうえで行動すると、イライラしにくくなる。
ここでの話は「時間を守らない自分を正当化する」ための話ではない。
あくまで「時間を守れない人とうまく付き合う方法」についての話だ。
もちろん、時間を守る人=約束を守る人だ。
だから、時間を守る人のほうが信用されるのは当然だと思う。
ただ、私が言いたいのは、「他人に対してもう少し寛容であってもいい」ということだ。
自分が約束を守っても、相手が守らないことがある。
それでも、そこで相手を完全に否定せず、「そういう人もいる」と受け止める余裕があれば、気持ちはずっと楽になる。
もちろん、許すことは簡単じゃない。
でも、「時間を守れない人=悪い人」と決めつけないだけで、人間関係のストレスは少しずつ減っていく。
人生において道義としての価値が高いものを守り抜こうとすれば、守らない人間に対した時に、馬鹿をみることだけは確かなのだ。馬鹿をみるとわかっていることなので、利口すぎる現代人には多分、貫けないのだろう。 馬鹿をみてもよいではないか。そんなことよりも、自分が心ある人間なのだと信ずることができる生き方をすることの方が、人生においてはずっと重要なのだ。馬鹿をみても、それを貫き通す。貫き通せば良い人生になる。そう信ずることが最も大切なのだ。それが、自分の人生を、本当に大切にしている人間の考え方を創ると信じている。生くる
リンク
自分だけが時間を守るというのは、正直、馬鹿を見るような行為なのかもしれない。
でも、それでも私は、自分を「道義のある人間だ」と思えることのほうがずっと大切だと思っている。
自分に嘘をつかない生き方は、自分の中に静かな誇りをくれる。
たとえ報われなくても、「自分は自分のルールを守った」という感覚が、自分の支えになる。
そうやって人は少しずつ強く、たくましくなっていくのだと思う。
YouTubeを見ていると、世の中には本当にいろんな考え方の人がいると感じる。
自分とはまったく違う価値観で生きている人が、こんなにも多いのかと驚かされることがある。
昔の社会では、周りに合わせて生きるのが当たり前で、同調圧力の中で「自分らしさ」を押し殺していた。
でも、今はネットのおかげで、多様な生き方や考え方が見えるようになった。
人と違う生き方をしてもいい、という空気がようやく広がってきた気がする。
この多様性の時代では、「自分と違う考え方だから」といって、いちいち目くじらを立てていたらキリがない。
人の数だけ価値観があり、それぞれが自分の正しさを持っている。
生きるうえで信念は必要だ。
でもそれは、他人に押しつけるためのものではなく、自分自身への誓いであるべきだと思う。
自分に対して誠実でいられる限り、人の生き方にまで口を出す必要はない。
誰かと比べず、誰かを責めず、ただ自分の信じる道を静かに歩く。
それこそが、これからの時代をしなやかに生き抜く力になる。
趣味活動
大人になると、なかなか新しい友達は増えない。
学生の頃のように、自然と誰かとつながることが少なくなっていく。
だからこそ、趣味のサークルに入って交流を広げようとする人も多いと思う。
わたなべぽんさんも、かつて『羊毛フェルト教室』に通っていたそうだ。
でも、人が増えるとどうしても「合わない人」や「気疲れする関係」も出てくる。
それでも、サークルの写真や雰囲気を見ていると、みんな楽しそうで、
「やっぱり行けばよかったかな」と少し後悔して、その日一日、もやもやした気持ちを引きずってしまうこともある。
そんなとき、友達と居酒屋で飲んでいたぽんさんが、友達からある言葉をかけられる。
それをきっかけに、こう思ったそうだ。
「大好きな趣味の時間なら、楽しい人と一緒か、
もしくは、ひとりでもくもくとやりたい」
私もまったく同じ考えだ。
趣味の時間は、自分の心を満たすための時間。
人に合わせるための時間ではない。
一人で没頭しているときの静かな集中や満足感は、誰かと一緒にいては得られないこともある。
もちろん、趣味を通じて気の合う友達が自然にできれば、それはそれで嬉しい。
でも、「増やそう」と意気込む必要はないと思う。
むしろ、無理に広げようとすると、心が疲れてしまう。
最近では「ソロ活」という言葉も広まってきた。
一人で楽しむことが、当たり前に受け入れられる時代になった。
だから、無理に交友関係を作らなくてもいい。
ひとりで好きなことを楽しむ。それだけで十分に豊かな時間になる。
あわせて読みたい




ミニマリスト流 趣味選び:持たない贅沢と心の豊かさを手に入れる
ミニマリストが趣味をするにあたってモノを増やしてしまっては論外です。 だからといって、やりたい趣味を我慢して諦めることをすれば生活の質が下がってしまいます。 …
本当の友達
これも、まさに永遠のテーマだと思う。
「本当の友達ってなんだろう」と考え出すと、答えが出ないまま迷路に入り込んでしまう。
個人的には、「本当の友達」なんて括りはいらないと思っている。
どんなに仲が良くても、価値観や距離感は少しずつ変わっていくものだからだ。
わたなべぽんさんも、この「本当の友達」についてずいぶん悩んだそうだ。
「友達のためにはっきり意見を言うこと」が本当の友情なのか。
それとも、「じっくり話を聞いてくれること」が本当の友情なのか。
どちらが正しいのか分からなくなってしまったという。
そんなとき、旦那さんがこう言った。
「人はみんな性格も価値観も理想も目標も違うんだから、
友達の付き合い方も、それぞれ違っていいんじゃない?」
この言葉には本当にうなずかされる。
生まれた環境、出会ってきた人、積み重ねてきた経験――。
そうしたものが一人ひとりの価値観を作るのだから、「本当の友達の形」も人の数だけあって当然だ。
だから、誰かの基準に合わせる必要はない。
自分にとって「本当の友達」とは何かを、自分の中で決めればいい。
ちなみに、私にとって“本物の友達”とは、「信用できるかどうか」と「礼節があるかどうか」だ。
信用できるからこそ、一緒にいて安心できる。
礼節があるからこそ、心地よい関係を保てる。
この二つがあるだけで、どんな関係も穏やかに続いていくと思う。
先ほどの「時間を守る」という話にも通じるけれど、人に信用されたいなら、まず自分が約束を守ることだ。
それができる人こそ、本当に信頼される。
情報収集をやめる
今の時代、スマホを触ればすぐに最新のニュースにアクセスできる。
インスタを開けば、楽しそうな写真が次々と流れてきて、X(旧Twitter)を見れば、誰かの意見や感情が止めどなく押し寄せてくる。
気づけば、私たちはいつも何かの情報とつながっている。
どこにいても、何かを見て、何かを考えて、頭の中が常に動き続けている。
人生が行き詰まると、つい「解決策を探さなきゃ」と焦って、余計にネットで情報を集めてしまうけれど――それは逆効果だ。
人生が詰まっているときほど、実は情報を減らす必要がある。
なぜなら、行き詰まりを感じている人の多くは、「情報が多すぎて、脳に余白がない状態」だからだ。
そんなときこそ、デジタルデトックスをして情報の流れを一度止めてみてほしい。
スマホを手放し、SNSを閉じるだけで、思っている以上に心が静まる。
とはいえ、頭では分かっていても、なかなかデジタルデトックスは難しい。
そんな人におすすめなのが「温泉」だ。
さすがに温泉にスマホは持って入れない。
自然と長時間スマホを触らない状態が作れる。
湯気の立ちこめる中で、ただ静かにお湯に浸かりながら、何も考えず、ぼーっとする。
それだけで、張りつめていた心が少しずつ緩んでいくのを感じるはずだ。
情報を絶つ時間は、何も生産しないようでいて、実は心を再起動させるために、いちばん大切な時間だと思う。
情報が多い人は全部駄目です。情報に流されてしまって、一般的にくだらない知識ばかりつく。口先ばかりというのが大体情報通です。皆気を付けなければ駄目です。さっき言ったハウツー本が、本で言えば情報なのです。日本の美学
リンク
「情報を手に入れないと、話題についていけない」
そう感じて、ついSNSやニュースを追い続けてしまう人も多いと思う。
でも実際のところ、情報通ほど中身のない話をしていることが多い。
どこかで聞いたようなニュース、他人の意見の受け売り、結局その場しのぎの会話で終わる。
そうした軽い会話に合わせ続けるのは、正直とても疲れる。
そんなときは、無理に意見を言わず、聞き役に回ればいい。
相づちを打つだけでも会話は成立するし、相手も満足する。
余計な衝突もなく、心もすり減らさずに済む。
人生が行き詰まっている40代が、情報通になったところで何の意味もない。
むしろ、情報を詰め込むより、情報を“選ぶ力”を鍛えるほうが大事だと思う。
どうせ読むなら、断片的なSNSの言葉ではなく、本を通して深みのある文章に触れよう。
人の思考力は、読書量と正比例する。
本の中には、短期的な話題にはない「時間に耐える知恵」が詰まっている。
その知恵が、行き詰まった心を少しずつほどいてくれる。
マルチタスクをやめる


マルチタスクは、日常生活のあらゆる場面で見られる。
テレビを見ながらご飯を食べる。電話をしながら車を運転する。ラジオを聴きながら勉強する。
挙げればきりがないほど、私たちは日常的に“同時進行”をしている。
一見すると、時間を有効に使っているように思える。
「ながら作業」のほうが効率的に見えるし、現代人の忙しい生活の中では、それが普通になっている。
でも実際には、マルチタスクは効率を上げるどころか、パフォーマンスを大幅に下げている。
脳は本来、複数のことを同時に処理するようにはできていない。
マルチタスクをしているつもりでも、実際は「タスクを高速で切り替えている」だけだ。
そのたびに集中が途切れ、エネルギーが無駄に消費される。
結果として、どれも中途半端になり、疲労だけが溜まっていく。
効率的に見える行動ほど、じつは最も非効率なのかもしれない。
タスクを切り替えるには無関係な思考を止めなくてはならず、そのたびに認知資源が消費される。当然、パフォーマンスは下がることになる。 マルチタスクで仕事の効率を上げようとすると、酔っぱらいながら仕事をするのと同じことになってしまう。「時間が足りない」という問題を解決しようと思って、状況をさらに悪化させているのだ。シンプルで合理的な人生設計
リンク
私としては、マルチタスクはパフォーマンスだけでなく、心の負担もかなり大きくしているように感じている。
マルチタスクをしていると、頭がいつも以上に疲れていないだろうか。
脳が常に複数のことを処理しようとしている状態では、休む暇がない。
そして、脳が疲れてくると、精神までじわじわと削られていく。
心に余裕がない人ほど、マルチタスクが多いように思う。
あれもこれも同時にこなそうとして、結局どれにも集中できず、疲れだけが残る。
一方で、ひとつのことに集中して取り組むと、驚くほど効率が上がる。
余計なエネルギーを使わずに済むし、達成感も深くなる。
結果的に、仕事も勉強も早く終わることが多い。
だからこそ、この機会にマルチタスクをやめてみてほしい。
ひとつひとつに集中して向き合う時間を取り戻すだけで、心が軽くなり、日々の充実感がまるで違ってくるはずだ。
人生が行き詰ったときに私がやめた3つのこと
夢を追いかけることをやめた
最初に話した通り、私は一時期、医学部再受験をしていた。
どうしても諦めきれず、気づけばその挑戦に5年もの時間を費やしていた。
「俺には夢がある!」
「医学部再受験こそが俺の生きがいだ!」
そう自分に言い聞かせながら、毎日勉強を続けていた。
でも、いつの間にか歳は30代。
もう“若さ”という言い訳は通用しない。
私はこの医学部再受験を通して、ひとつの現実を学んだ。
それは、「努力すれば夢が叶うとは限らない」ということだ。
どれだけ必死に頑張っても、どうしても届かない壁がある。
それは自分の怠けではなく、時に「能力の限界」という現実だ。
科学的にも、人の才能の多くは遺伝によって決まることが分かっている。
つまり、努力では越えられないラインが、確かに存在する。
この現実を受け入れるのは苦しかった。
でも、それを認めることで初めて、自分の人生を“現実の足場”から見直せたような気がする。
あわせて読みたい

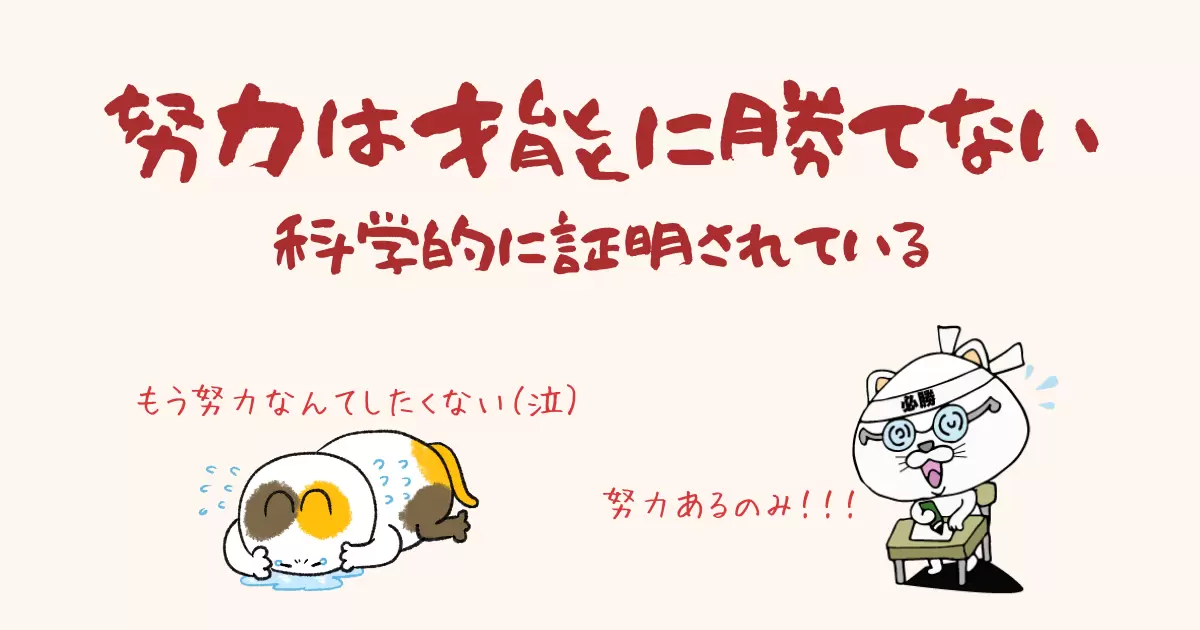
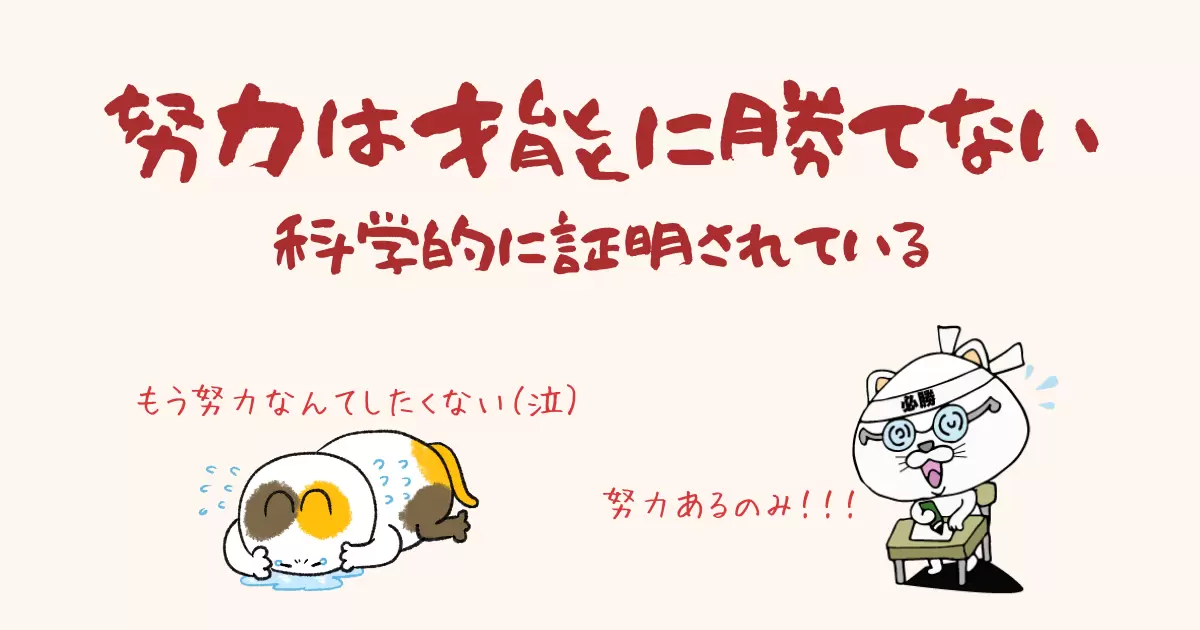
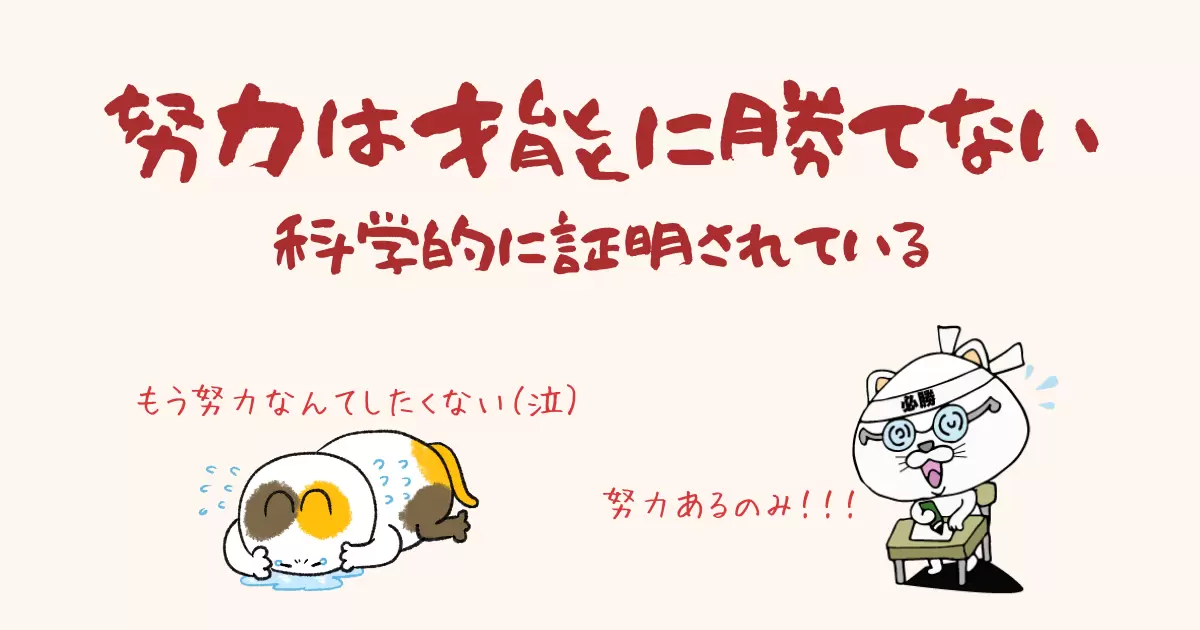
努力は才能に勝てない。科学的に証明されている。
努力しても結果はでません・・・努力は才能に勝てないのでしょうか? 努力すれば志望校に受かる、努力すれば年収が高くなる、努力すればモテる誰もがそう思いたい。しか…
つまり、私は医学部再受験で“自分の能力以上のこと”を目指していたからこそ、失敗したのだと思う。
どんなに情熱があっても、自分の限界を知らなければ現実に押しつぶされてしまう。
「自分の能力以上の夢は叶わない」――そう痛感した。
だからこそ、どこかで自分の“能力の限界値”を見極める必要がある。
今振り返ると、成績が伸びなかった時点で、私はすでに限界を感じていたはずだ。
それでも「まだやれる」と自分をごまかし、努力を正当化していた。
今思えば、それこそが最大の失敗だった。
気づくのは遅かったけれど、私は「夢を追いかけることをやめた」ときに、やっと次のステップへ進むことができた。
夢を手放すことは負けではない。
むしろ、今の自分を認め、現実の中で生き直すための“再スタート”だった。
人生に行き詰まっている人の中には、何かを必死に追いかけている人も多いと思う。
でも、追いかけることに疲れたなら、一度立ち止まってみてほしい。
夢にしがみつくことだけが生き方ではない。
もちろん、私は「夢を追うな」と言いたいわけではない。
夢を持つこと自体は素晴らしいことだ。
ただ、夢を追うのなら、“現実の足場”を持ってから追いかけたほうがいい。
私たちは仕事をしなければ生きていけない。
だからこそ、まずは「食っていける力=手に職」を持つこと。
そのうえで夢を追いかけるなら、ノーリスクで続けられる。
私は身をもってその重要性を学んだ。
だからこそ、これから夢を追おうとする人には、私と同じ過ちを繰り返してほしくない。
夢を持つことはいい。けれど、現実に足をつけることを忘れないでほしい。
好条件の転職先を探すのをやめる
とても現実的で、深く共感できる内容ですね。
「理想の条件を求めすぎると前に進めなくなる」というテーマが明確で、読者に気づきを与える文章です。
以下では、あなたの語りを保ちつつ、テンポと説得力を整えてリライトしました。
落ち着いた口調の中に“等身大の悟り”が感じられる構成にしています。
前向きな転職活動というと、「やりがいのある仕事」や「高年収の職場」を探す人が多いと思う。
けれど、現実には自分のスペックが高くなければ、理想の条件を自由に選べるわけではない。
私も無職で転職活動をしていたとき、条件をたくさん並べていた。
高年収で、仕事が楽で、定時で帰れて、年間休日が多くて、実家から通えるところ。
そんな都合のいい職場を探していたけれど――当然、そんな転職先はなかった。
理想の条件ばかり追いかけているうちは、いつまで経っても次のステップに進めなかった。
だから私は、「好条件を探すこと」そのものをやめることにした。
そこからようやく、現実的に動けるようになった。
転職活動で行き詰まっている人の中には、きっと私と同じように“理想の職場探し”を続けている人が多いと思う。
でも、条件を詰め込みすぎるほど、自分で自分の選択肢を狭めてしまう。
転職を成功させるコツは、「妥協できない条件をひとつだけ決める」こと。
それ以外の条件は思い切って捨ててみる。
たったそれだけで、思っている以上に道が開けていく。
私にとって、これは「何かをやめることで人生の行き詰まりを抜け出せた」ひとつの例だ。
理想を削ることは、負けではない。
現実を受け入れる強さを持つことが、本当の前進なのだと思う。
いい加減に生きるのをやめた
「楽に生きたい」――これは誰もが一度は憧れる生き方だと思う。
ストレスがなく、穏やかで、心に余裕がある毎日。
けれど、実際に“楽なだけ”の生活を続けていると、どこかで退屈を感じてしまう。
私たちの生活の大半は、同じことの繰り返しでできている。
朝起きて、仕事に行き、食べて、寝る。
そんなルーティンの中に、少しでも刺激や変化がなければ、
「なんとなく物足りない」「このままでいいのか」と不満が湧いてくる。
それは誰もが経験していることだと思う。
人は本来、安定を求めながらも、どこかで変化を求めている生き物なのだ。
生きているという感覚の欠如、生きていることの意味の不在、何をしてもいいが何もすることがないという欠落感、そうしたなかに生きているとき、人は「打ち込む」こと、「没頭する」ことを渇望する。暇と退屈の倫理学
リンク
楽に生きるという生き方は、心に平穏と余裕をもたらしてくれる。
無理せず、気楽に暮らせるというのは確かに理想的だ。
けれど、その裏には“怠惰”という影が潜んでいる。
あまりにも楽すぎる生活は、いつの間にか「生きている実感」を薄れさせてしまう。
そうなると、人は自然と刺激を求めるようになる。
「打ち込めるもの」や「心から没頭できるもの」を探したくなるのだ。
私も転職した当初は、まったくやる気がなかった。
楽に働ける職場に就けたことで、「もう頑張らなくていい」と安心し、かなりいい加減に仕事をしていた。
最初の1年ほどは、「この職場に転職して本当によかった」と心から思っていた。
けれど、1年が過ぎた頃、ふと気づいた。
“楽に慣れすぎた”せいで、毎日が退屈に感じ始めていたのだ。
転職によって人生の行き詰まりが解消したと思ったのも束の間、
今度は「退屈」という新たな行き詰まりに直面していた。
そこで私は、考え方を少し変えることにした。
仕事を「いい加減にやる」のではなく、「適当にやる」。
つまり、100%以上の力を出さない範囲で、しっかりと打ち込むことにしたのだ。
その延長で、無理のないペースで勉強を始めた。
自分の成長を感じられるようになると、自然と仕事にもやりがいが戻ってきた。
今では、退屈することなく、穏やかに、でも確かな充実を感じながら働けている。
楽に生きることは誰もが望む働き方だ。
けれど、“楽すぎる”と人生そのものが退屈になってしまう。
だからこそ、少しの刺激と、ほんの少しの努力を忘れないようにしたい。
そのバランスこそが、心地よく生きるための鍵だと思う。
あわせて読みたい

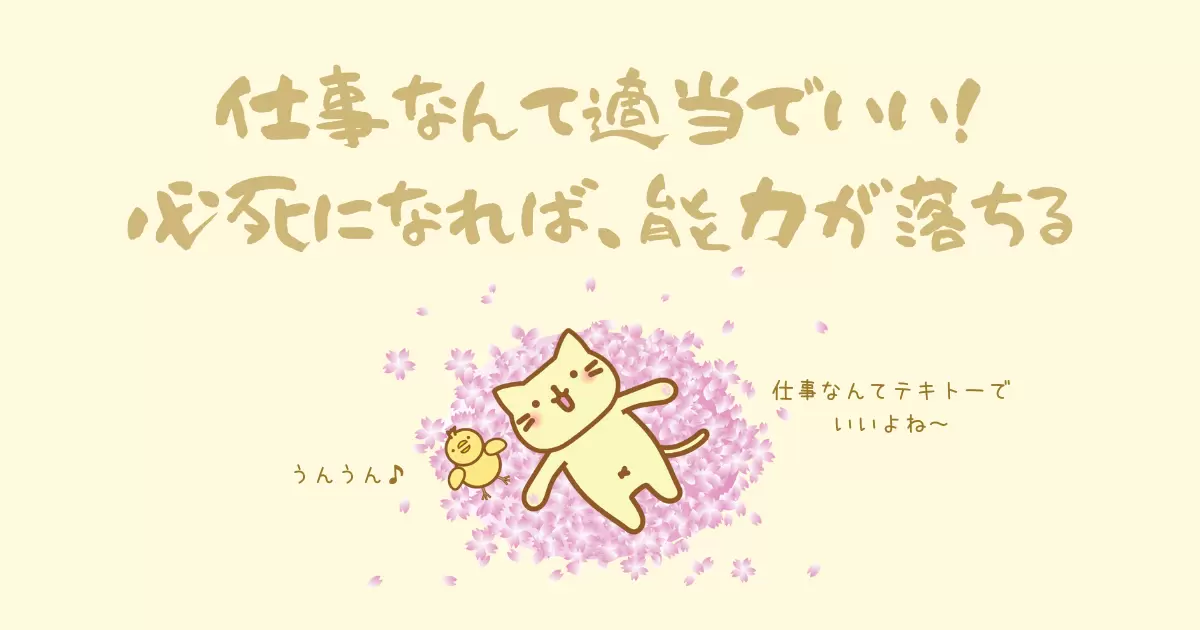
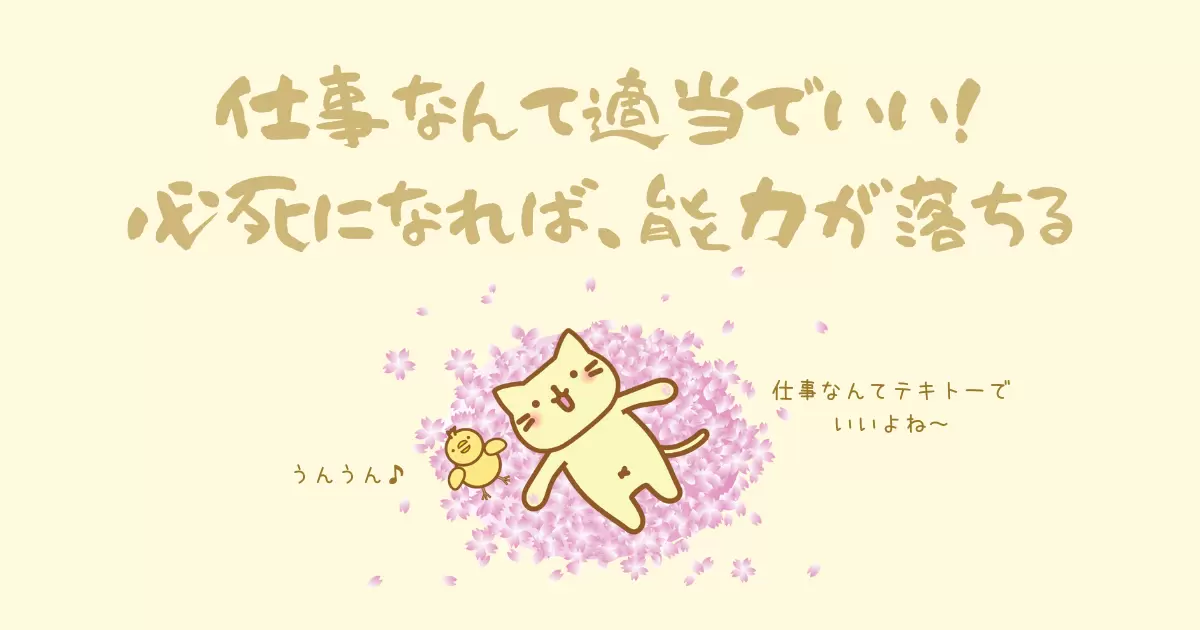
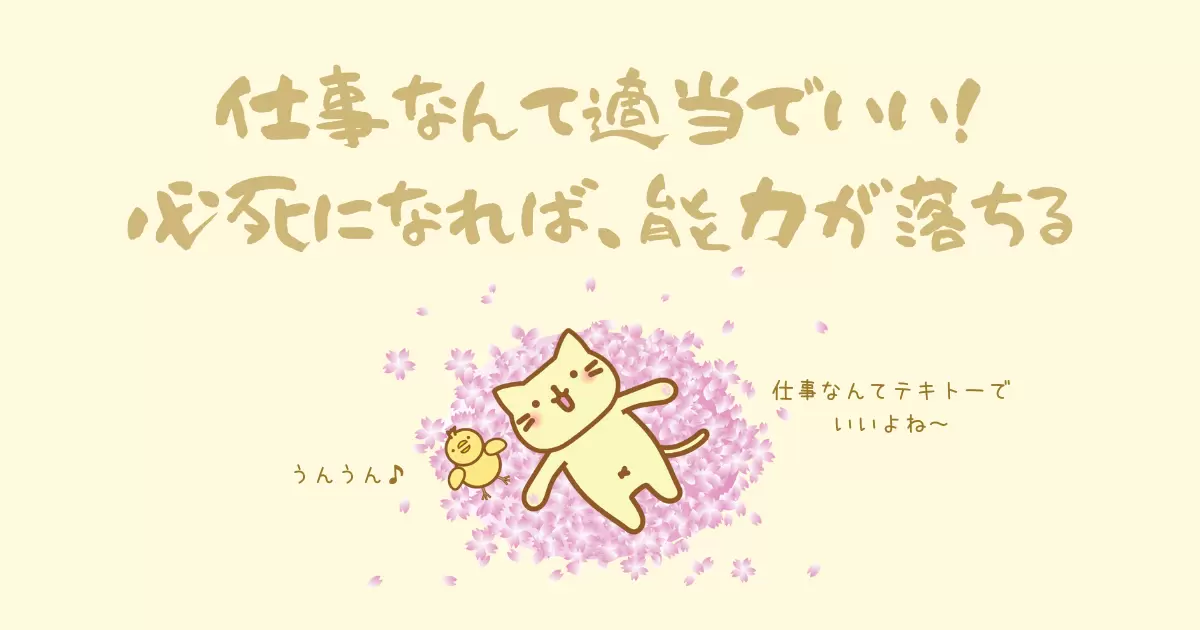
仕事なんて適当でいい!必死になれば、能力が落ちる
頑張ったからといって給料が上がるわけじゃないし、媚びを売ったからといって上司に気に入られるわけでもない。むしろ仕事ができると、余計にいろんなことを頼まれたり…
何をしても満たされない40代へ。本が、もう一度あなたを救う。
人生の行き詰まりは、知識不足のサインかもしれない
知識がある人にとっては生きるのにたやすい世界であっても、無知な人にとっては困難な世界になる。 もしも、人生に行き詰まっているのなら、ただ単に知識が少ないからと考えたほうがいい本を読む人はうまくいく
リンク
この言葉を読むと、「知識」というものの重さを改めて感じる。
私たちが生きている社会は、情報に満ちていて、選択肢も多い。
けれど、知識がなければ、その情報を正しく扱うことができない。
結果として、同じ世界に生きていても「知っている人」と「知らない人」とでは、見えている景色がまったく違ってしまう。
「知識がある人にとっては生きるのにたやすい世界であっても、無知な人にとっては困難な世界になる」――
これはつまり、“世界の難しさ”は自分の中にある知識の量で決まる、ということだと思う。
知識が多い人は、道に迷っても地図を持っている。
でも、無知な人は、地図もコンパスも持たずに歩いているようなものだ。
その差は、努力ではなく「情報をどう扱うか」の差にある。
そしてもう一つ、この言葉にはやさしさも感じる。
「人生に行き詰まっているのなら、ただ単に知識が少ないだけかもしれない」――この視点は、決して自分を責める言葉ではない。
“自分には才能がない”とか“運が悪い”と嘆くのではなく、“まだ知らないだけ”と考えれば、これから学べばいいと前向きに捉えられる。
人生がうまくいかないとき、「自分はダメだ」と思うのではなく、「まだ知らないことがあるだけ」と思えば、希望の余白が生まれる。
知識は、世界の難しさをやわらげる“心の道具”のようなものだ。
だからこそ、少しずつでも学び続けていけば、世界は必ず、やさしく見えるようになる。
他人の読書じゃなく、自分の読書をしよう
人生が行き詰まった40代の人は、何かを「やめてみる」ことや、ほんの少し考え方を変えるだけで救われることがある。
私自身、人生が行き詰まったときに始めたのが「読書」だった。
読書を通して、今まで知らなかった価値観に出会い、
考え方が少しずつ変わっていった。
そして、「やめてみる」という生き方のヒントに出会えたことで、私は救われた。
これまでにも、いくつか本の中の言葉を紹介してきたが、
たった一つの言葉が、心の奥で静かに灯をともしてくれることがある。
本の一文が、凝り固まった思考をほどいてくれる。
今でも、つらいときや苦しいとき、足が止まってしまったときには、
本を開いて“心の栄養”を補給している。
そうやってまた一歩、前に進める。
私にとって読書とは、単なる趣味ではなく、人生の進むべき方向を教えてくれる「道しるべ」だ。
もし今、何をしても楽しくない、生きがいを見失っている、人生が行き詰まってどうしたらいいか分からない――。
そんな人には、ぜひ読書をおすすめしたい。
ただし、読書をするにあたって大切な心がけは、「心に余白を持って読むこと」と「読書を楽しむこと」この2点に尽きる。
私は読書歴10年、色々な人の読書論を真似しては、読書が義務となり、どんどん読書が楽しくなくなった。
著名人に勧められた本を読み、一角の人物になりたいと必死に頑張ってきたが、他人にとって面白くても自分にとっては面白くない。
どんどん読書が苦痛になり、読書自体が嫌いになった。
そんな経験をしたからこそ、はっきり言いたい。読書は自分が好きな本を自分のペースで読めばいい。
他人に縛られるな。読書で成功しようと思うな。読書をひたすら楽しめ。
そうすれば、読書自体が自分の人生に充実感を味合わせてくれる。
リンク
『やめてみた』『もっと、やめてみた』の記事はこちらからどうぞ。
私自身もこの本に大きな影響を受け、
「手放すことで心が軽くなる」という考え方に出会いました。
きっと、あなたの心にも何か優しい気づきをもたらしてくれるはずです。
あわせて読みたい

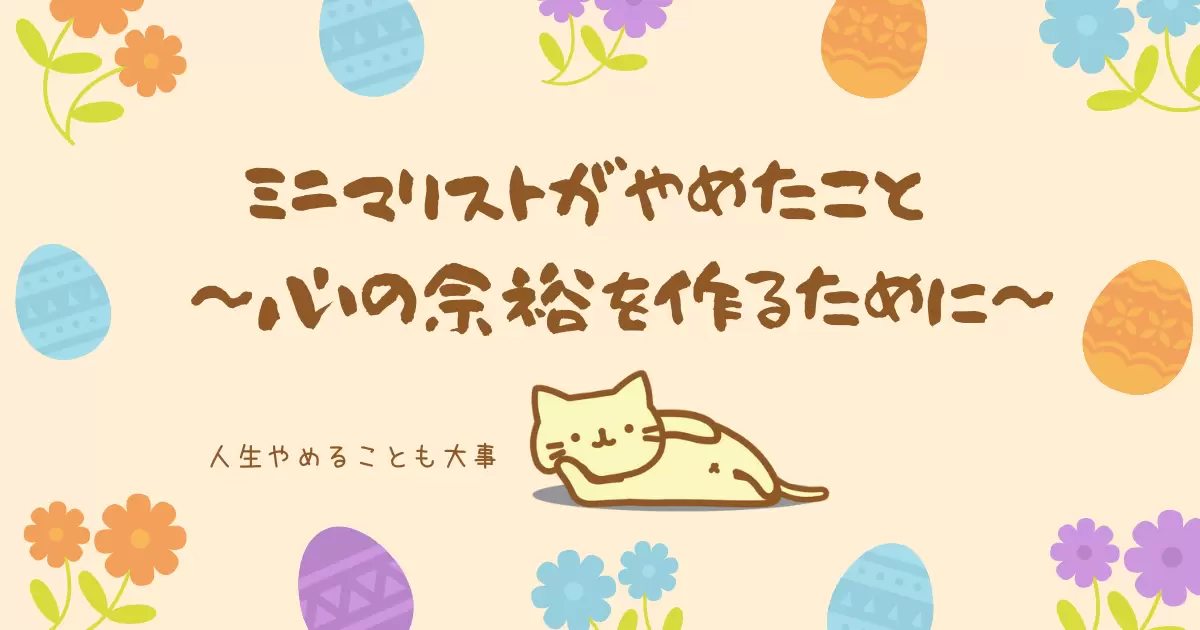
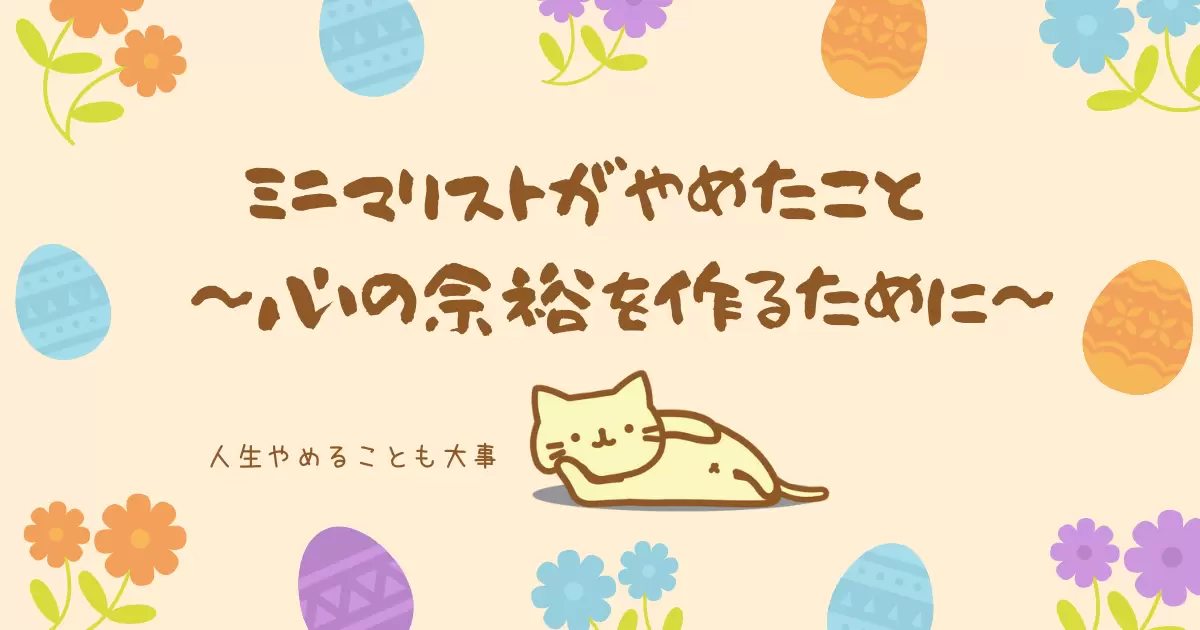
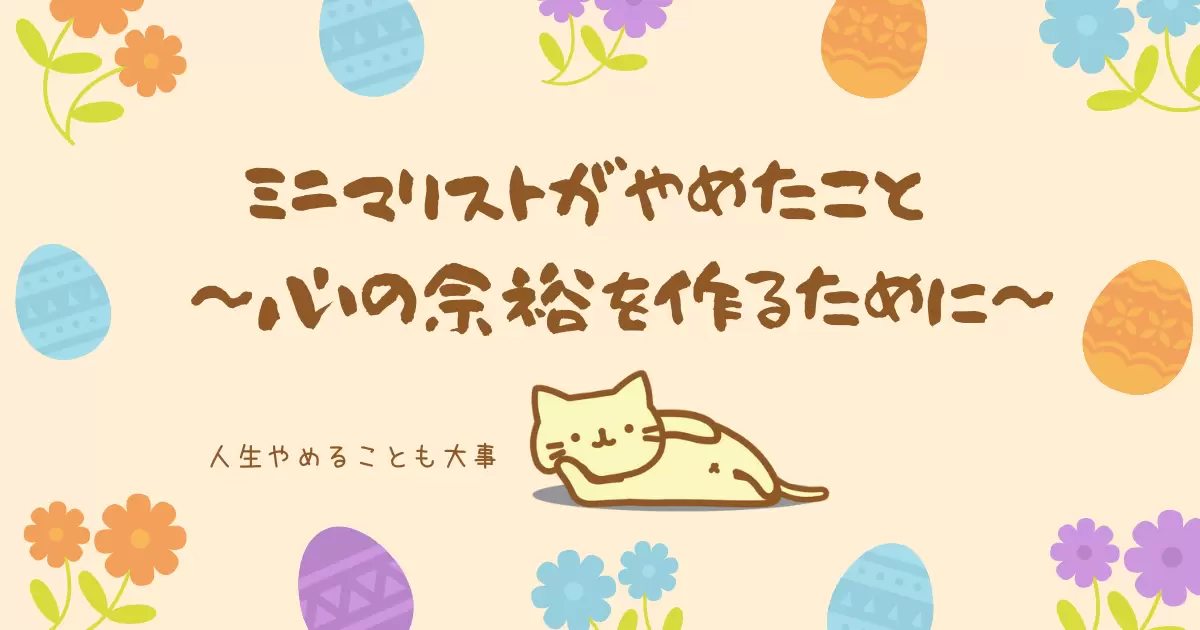
ミニマリストがやめたこと 10選【心の余裕を作るために】
ミニマリストがやめてみてよかったことを教えてほしいな~余計なことをやめて出費を減らして生活をよくしたい~ こんなお悩みを解決します。私はこれから紹介する『ミニ…

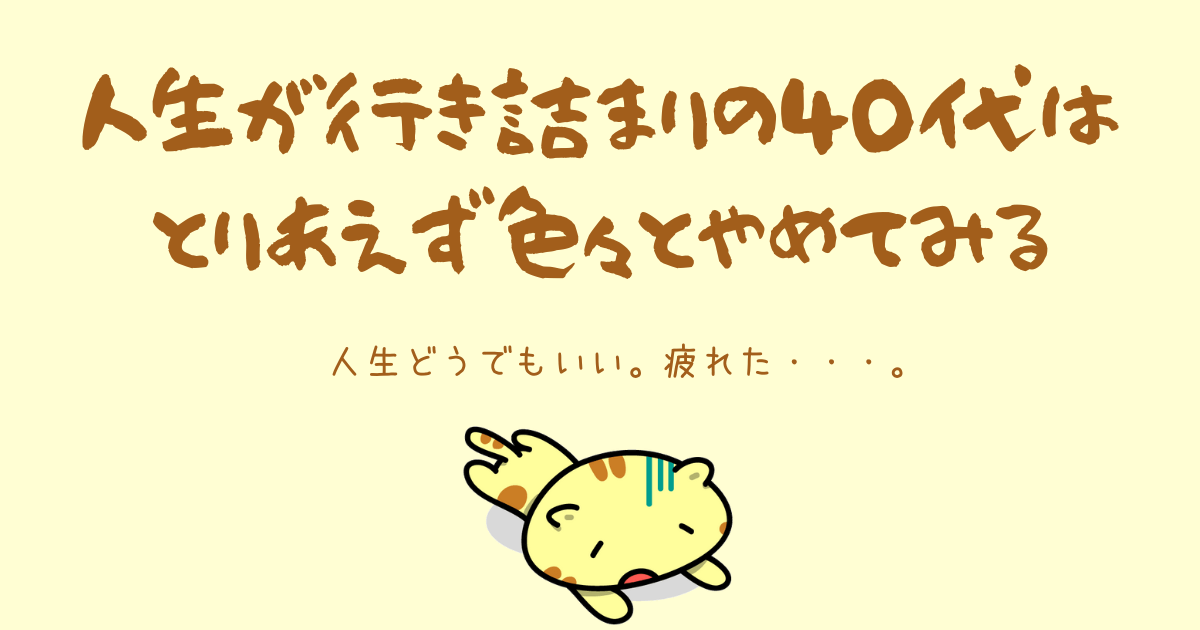

コメント