幼い頃から、私は一生懸命努力した人たちがスポーツで活躍し、成績も良いことを目の当たりにしてきた。
アニメや漫画を見て育った私は、「努力すれば夢は叶う」と信じていた。
努力した人だけが希望の大学に進み、努力しなかった人は「Fラン」と呼ばれるような大学にしか行けない。
そんな現実を見て、「結局、努力できるかどうかが人生を分けるんだ」と思っていた。
社会に出ると、年収の差という形でその現実をさらに突きつけられる。
努力した人は報われ、努力できない人は「給料泥棒」と陰で言われる。
そんな構図の中で、私は「努力すれば何でも思い通りになるのか?」と自問するようになった。
今の私は、努力すれば夢が叶うというのは、あくまでアニメや漫画、ドラマや映画といったフィクションの中だけの話だと思っている。
人は「努力すれば報われる世界」を信じたいからこそ、そういう物語を作り、消費しているのだと思う。
大人になった私は、現実のほうがずっと複雑だと知った。
努力しても夢が叶わないこと。
努力しなくても、運次第でうまくいくこと。
どれだけ限界を超えて頑張っても、報われないこと。
人生で本当に大切なのは、理想の中で生きることではなく、現実を体験として理解していくことだと思う。
現実の世界では、がむしゃらに働く人よりも、うまく力を抜いて働ける人のほうが結果を出すことが多い。
ここでいう「適当」とは「いい加減」ではなく、「自分の限界を見極めて、ちょうどいい力加減でやること」だ。
適当に仕事をする人は、自分を追い込みすぎない。
だから、心に余白が生まれ、視野が広く保てる。
その余裕が、思考をクリアにし、「今、自分が何をすべきか」を見極める力につながる。
あせってはいけません。ただ、牛のように、図々しく進んでいくのが大事です。
夏目漱石
焦って仕事をするのは禁物だ。
ここでは、なぜ仕事が適当な人ほど仕事ができるのか、その理由を詳しく解説していく。
目次
適当な人は仕事できる!
硬直思考よりも柔軟な思考の方が仕事が早く進む

仕事を必死にやる人の頭の中には、「こうでなければならない」「こうすべきだ」という強い思い込みがある。
良い言い方をすれば信念、悪く言えば硬直した考え方だ。私はそういうタイプの人をたくさん見てきた。
このタイプの人は、自分に厳しく、他人にも同じ厳しさを求める。だから衝突が多い。
真面目で努力家なのに、なぜか周りとうまくいかないのはそのせいだと思う。
一方で、仕事を“適当に”やる人は、そこまで硬直しない。
「まぁいいか」と思える余白があるからだ。
この“まぁいいか”は怠け心じゃなくて、心の柔軟さだ。
私は、一生懸命すぎていつも張りつめている人を見ると、こちらまで息が詰まる気がする。
自分の考えに縛られすぎて、顔がこわばっている。そんな人と一緒に仕事をするのは正直つらい。
一生懸命なのは悪いことじゃない。
でも、心に余裕のない一生懸命は、周りを疲れさせる。
仕事は一人で完結するものじゃなく、チームで支え合うものだ。
自分の考えを押しつけたり、「自分が正しい」と思い込むのは、仕事をするうえで大きな障害になる。
人間関係のトラブルの多くは、この“押しつけ”から生まれている。
誰かと争ったところで、職場の雰囲気が悪くなり、結果的に自分も働きづらくなるだけだ。
禅の言葉に「柔軟心」というものがある。
自分の価値観こそ正しいという執着や偏見を手放し、柔らかくものを見る心のことだ。
私は、この考え方が好きだ。
思考が固まりやすい人には、本を読むことをすすめたい。
人から直接言われると反発してしまうことも、本を通してなら素直に受け入れられることがある。
本を読むことで、自分の中にいろんな視点が生まれる。
「そういう考え方もあるのか」と思える瞬間があるだけで、心は少し軽くなる。
そして、自分の考えが絶対じゃないと気づけたとき、人は少し優しくなれる。
だから私は、できるだけ多くの本を読むようにしている。
違う著者の考えに触れるたびに、自分の中の“柔軟心”が少しずつ育っていく気がする。
一生懸命は美しい

一生懸命に仕事をすることと、適当に仕事をすることは、たしかに矛盾しているように聞こえる。
でも、私が言いたい「一生懸命」とは、限界を超えて自分をすり減らすことではない。
私の思う一生懸命とは、自分なりの努力を最大限に尽くしながらも、その結果に執着しないことだ。
だからこそ、適当──つまり“いい度合いでやる”という感覚が必要になる。
真剣に取り組むけれど、無理をしない。
その絶妙なバランスの中に、心の安定と成長があると思う。
力を抜くのではなく、力の使い方を知ること。
それが本当の意味での「適当」だ。
結果にこだわりすぎると、心が壊れてしまう。
だから私は、「うまくいったか」よりも、「自分が一生懸命にできたか」を基準にしている。
努力の先にあるのは成功ではなく、納得なのかもしれない。
たとえ結果が出なくても、全力で取り組む人の姿はやっぱり美しい。
もし私がその人の同僚なら、応援したくなるし、自然と手を差し伸べたくなる。
人は“完璧な人”ではなく、“懸命に生きる人”に心を動かされるものだ。
ただ、一生懸命すぎると心の余裕がなくなり、周りとの関係がぎくしゃくする。
だからこそ、頑張りすぎず、手を抜きすぎず、「いい安牌」で生きることが大切だ。
その「いい安牌」は、自分の限界を知り、受け入れた人だけが持てる境地だと思う。
大人になると、「一生懸命なんてバカバカしい」と感じることもある。
でも私は、一生懸命に生きることこそ、人生をちゃんと味わうということだと思っている。
中途半端に流されるよりも、自分の意志で、熱をもって生きたい。
どうせ一度きりの人生なら、私は最後まで自分の力を出し切って、後悔のないように終えたい。
そして、その道のりの中にこそ、「いい加減」でも「まっすぐ」な生き方があると信じている。
心に余裕に生まれる
仕事を“適当に”するというのは、決して手を抜くことじゃない。
むしろ、自分の能力の最大値を引き出しながらも、限界を超えないようにコントロールすることだ。
だからこそ、心に余裕が生まれる。
人は8時間は眠らないと体も頭も持たないし、1日3食、栄養のあるものを食べなければエネルギーが枯れる。
そんな当たり前のことですら、限界を超えて働いている人にはできなくなる。
睡眠を削り、食事をおろそかにしてまで頑張るのは、一見ストイックに見えて、実は自分を削っているだけだ。
人の能力には個人差があり、それぞれに“ちょうどいい限界点”がある。
そこを超えて無理をすれば、一時的に成果が出たように見えても、長い目で見れば能力は確実に落ちていく。
つまり、限界を超える努力は、未来の自分の能力を食いつぶす行為なんだ。
トータルで見れば、限界を超えた分だけ仕事が早く終わるどころか、むしろパフォーマンスが落ちて成果は下がる。
これは根性論ではなく、単なる現実だ。
努力はもちろん大切だ。
でも、人には才能や向き不向きがある。
どれだけ頑張っても夢が叶わないこともある。
それなら、自分の能力が自然に発揮できる場所で“適当に頑張る”方が、ずっと健全で長く続けられる。
「適当」というのは、怠けることでも逃げることでもない。
むしろ、自分をちゃんと理解している証拠だと思う。
限界を知ることは、諦めではなく、成熟だ。
努力さえすれば何でも叶う――そんな幻想にいつまでも縛られる必要はない。
身の丈に合った働き方を見つけて、自分のペースで人生を歩むこと。
それこそが、心の余裕と幸福を守る一番の方法だと、私は思う。

あわせて読みたい

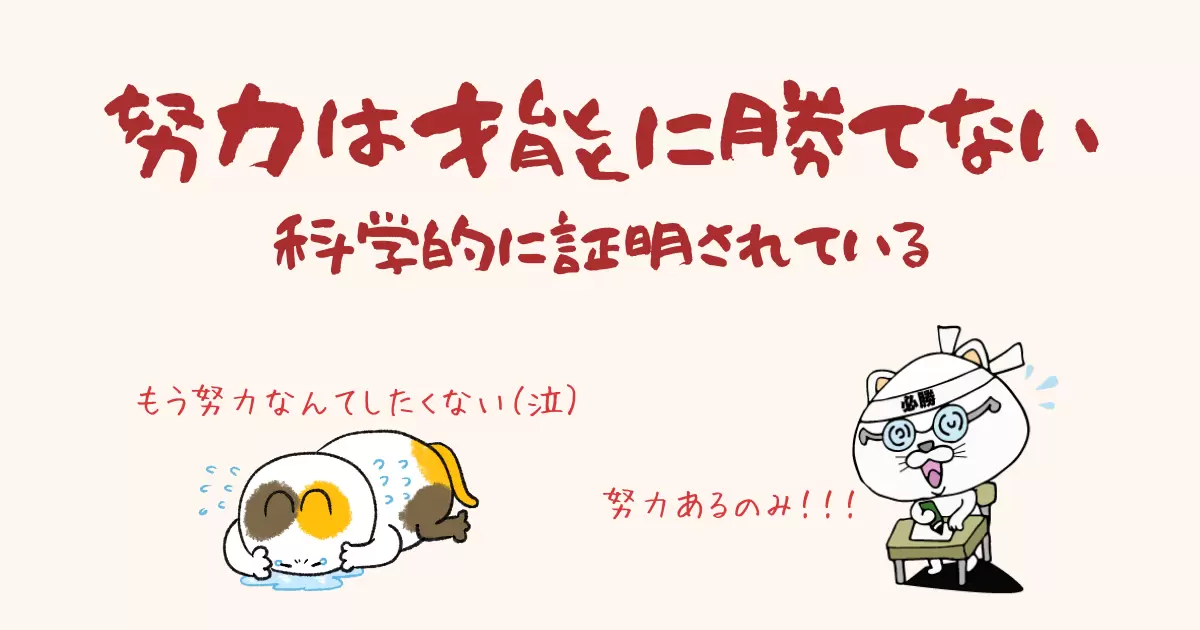
努力は才能に勝てない。科学的に証明されている。
努力しても結果はでません・・・努力は才能に勝てないのでしょうか? 努力すれば志望校に受かる、努力すれば年収が高くなる、努力すればモテる誰もがそう思いたい。しか…
自分の能力を最大限に発揮するためには、まず自分をすり減らさないことが大切だ。
仕事が嫌になったら思い切って休む。
しっかり8時間眠る。
3食を落ち着いて、味わいながら食べる。
そんな基本的なことを丁寧にこなすだけで、心と体の調子は見違えるほど変わる。
仕事を“適当に”やるというのは、サボることでも投げやりになることでもない。
それは、自分の心身をきちんとメンテナンスしながら働くということだ。
焦らず、無理せず、いいバランスで力を出す。
それこそが、最終的に一番大きな成果につながる。
結局、仕事の質を決めるのは「どれだけ頑張ったか」ではなく、「どれだけ健やかに続けられるか」だと思う。
だから私は、無理をして走り抜けるよりも、自分のペースで息を整えながら前に進んでいきたい。
自分を納得させられることが成果につながる

仕事を“適当にやる”というのは、怠けることじゃない。
それは、自分の努力を最大限に尽くして、そのうえで自分を納得させる生き方だ。
全力を出しきったうえで、「これでいい」と思える。
その感覚が、人生に静かな自信を与えてくれる。
もし何となく日々をこなし、いい加減に生きてきた結果、自分の中に何も残っていなければ――いつか必ず後悔する日がくる。
「何のために生きてきたんだろう」「何のために働いてきたんだろう」と。
けれど、毎日を自分なりに生き切っていれば違う。
どんな結果であっても、「私は十分やりきった。いつ死んでも後悔はない」と思える。
その感覚こそが、生きるうえで一番大切な報酬だと私は思う。
人生は一度きり。
同じ日は二度と戻らない。
だから、「あのときもっと頑張ればよかった」と後悔するよりも、今この瞬間をどう生きるかがすべてだ。
仕事を“適当にやる”というのは、自分の人生を肯定し、自分に誇りを持つということでもある。
限界を見極めながらも、できる範囲で最大限に力を尽くす。
それが、自分を納得させる一番まっとうな努力の形だと思う。
そして、その積み重ねが仕事の経験値を加速させ、気づけば以前よりずっと自然に、そして確実に仕事ができるようになっていく。
努力とは、本来そういう静かな進化のことを指すんだろう。
自分の目指すべきところが分かっている

仕事を“適当にやる”ためには、まず自分がどこを目指しているのかをはっきりさせる必要がある。
目標があいまいなままでは、何を手を抜き、どこに力を注ぐべきかの判断ができない。
なぜなら、8時間という限られた勤務時間の中で成果を出すためには、
「今、自分が成長するために何をすべきか」を明確にしておかなければならないからだ。
私たち凡人は、時間も体力も無限ではない。
だからこそ、自分の持つわずかなリソースを目標に向けて正しく使うことが大切になる。
あれもこれも手を出して器用にこなせる人なんて、ほんの一握りだ。
私たちにできるのは、自分の“これだ”と思える方向に力を集中させ、少しずつでも確実に積み重ねていくこと。
そうして初めて、ひとつのことを“それなり”にできるようになる。
仕事を適当にやるというのは、目標に向かって限られた時間を最適に使うことでもある。
つまり、それは怠けではなく、戦略的な働き方なんだ。
「エッセンシャル思考」は、自分や家族にとってなにがほんとうに大切( エッセンシャル)かを決め、優先順位の低いものを切り捨てて、やることを計画的に減らす。その結果、仕事や勉強の質が上がり、「ものごとをコントロールしている」「正しいことをしている」と思えるようになり、充実感をもって毎日を過ごせるようになる。シンプルで合理的な人生設計
リンク
エッセンシャル思考は、私のような凡人が才能ある人たちと並ぶための、唯一の手段だと思う。
すべてに手を出すのではなく、本当に大事なことだけに集中する。
それが、限られた時間とエネルギーで結果を出すための一番現実的な方法だ。
そのためには、まず自分が何をしたいのか、どこを目指しているのかをはっきりさせておく必要がある。
目的が見えていないと、ただ目の前の仕事を淡々とこなすだけになってしまう。
言われたことだけをやる働き方では、努力が成果に結びつかない。
けれど、目標があれば違う。
「どうすればもっと良くできるか」「もう一歩踏み込めるところはないか」と自然に考えるようになる。
その“+α”の意識が、自分の成長をつくり出す。
そもそも、+αで動かないと仕事は楽しくならない。
ただ与えられた作業をこなすだけでは、心が枯れていく。
自分で考え、自分の意思で仕事を少しでも良くしていくこと――
その積み重ねこそが、凡人にとっての“才能”なんだと思う。
あわせて読みたい

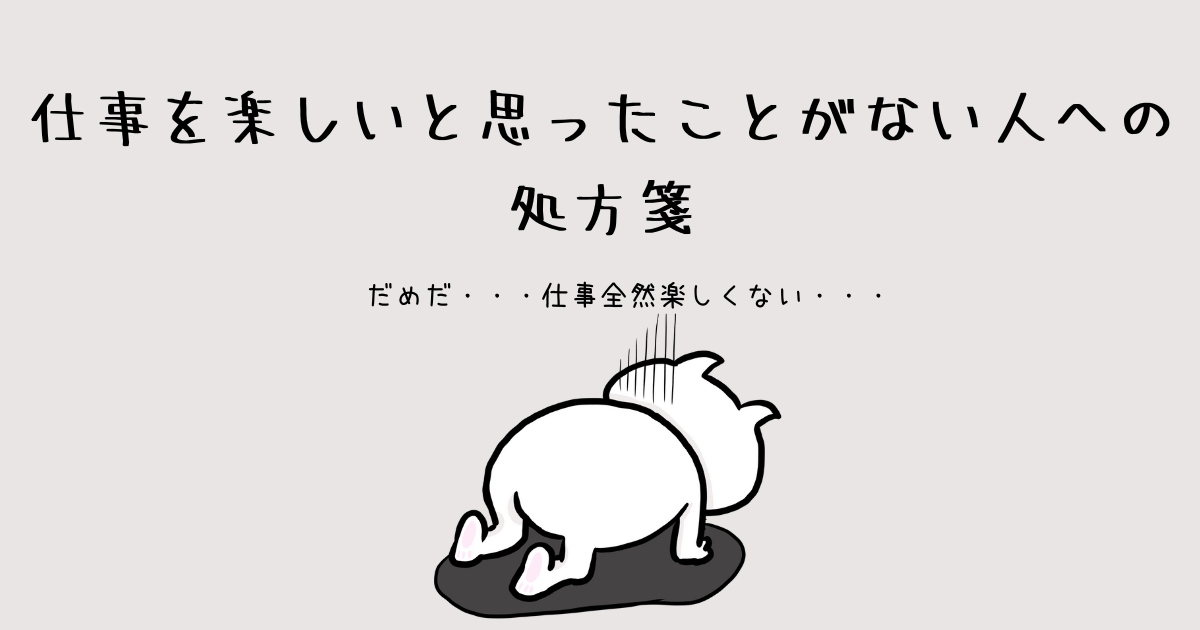
仕事を楽しいと思ったことがない人への処方箋
仕事は、内容によっては楽しいものではない。仕事には単純労働、肉体労働、知的労働などいろいろあるけれど、自分の性格に合っていないと、途端につまらなく感じてしま…
自分の努力を最大限に尽くすということは、裏を返せば、どこまでいっても限界があるということだ。
時間にも、体力にも、集中力にも、必ず終わりがある。
だからこそ、限られた努力で成果を出すには、やみくもに頑張るのではなく、自分なりに考えて行動することが大切になる。
私は老健で働く理学療法士だ。
何でも治せる“スーパー理学療法士”ではないし、その必要も感じていない。
私は老健というフィールドで求められることに焦点を当て、勉強する範囲を意識的に絞っている。
たしかに、病院や他施設に行けば、通用しない部分も多いかもしれない。
でも、私はそれでいいと思っている。
老健という現場で必要とされる専門性を深めることこそ、自分の力を最大限に活かす道だからだ。
何もかもを広く浅く知るより、目の前の現場で深く向き合い、自分にしかできない仕事を磨いていく。
その積み重ねが、私にとっての“努力の形”であり、“自分を納得させる生き方”でもある。
人間関係に悩まなくて済む

仕事を“適当に”最大限の努力でやろうとすると、自分の成長に意識が向く。
だから、自然と他人のことを気にしなくなる。
逆に言えば、いつも他人の言動ばかり気になる人は、まだ自分の仕事にしっかり向き合えていないのかもしれない。
一生懸命に仕事をしている人と、ダラダラといい加減に仕事をしている人。
あなたをイライラさせるのは、どちらだろう?
たぶん、真剣に取り組む人の方に対しては、イライラよりも“刺激”を感じるはずだ。
それが、人を本気にさせる力だと思う。
仕事を“適当にする”というのは、自分の姿勢だけでなく、周囲の評価や人間関係も変えていく。
もし今、人間関係で悩んでいるなら、一度まっすぐ仕事に集中してみてほしい。
自分の力を最大限に出し切ることに意識を向けると、他人の声が不思議と聞こえなくなる。
集中しているとき、頭の中は仕事のことでいっぱいになる。
他人への不満や嫉妬を考える余地なんて、どこにもない。
その静かな集中の時間こそが、心の安定を生み出す。
職場の人間関係で争うほど、時間の無駄はない。
言い争っても何も生まれないし、職場の空気が悪くなれば、結局は自分も働きにくくなるだけだ。
うまくやるコツは、他人を変えようとせず、自分の仕事に集中すること。
それが、最もシンプルで、最も効果的な人間関係の整え方だと思う。
あわせて読みたい

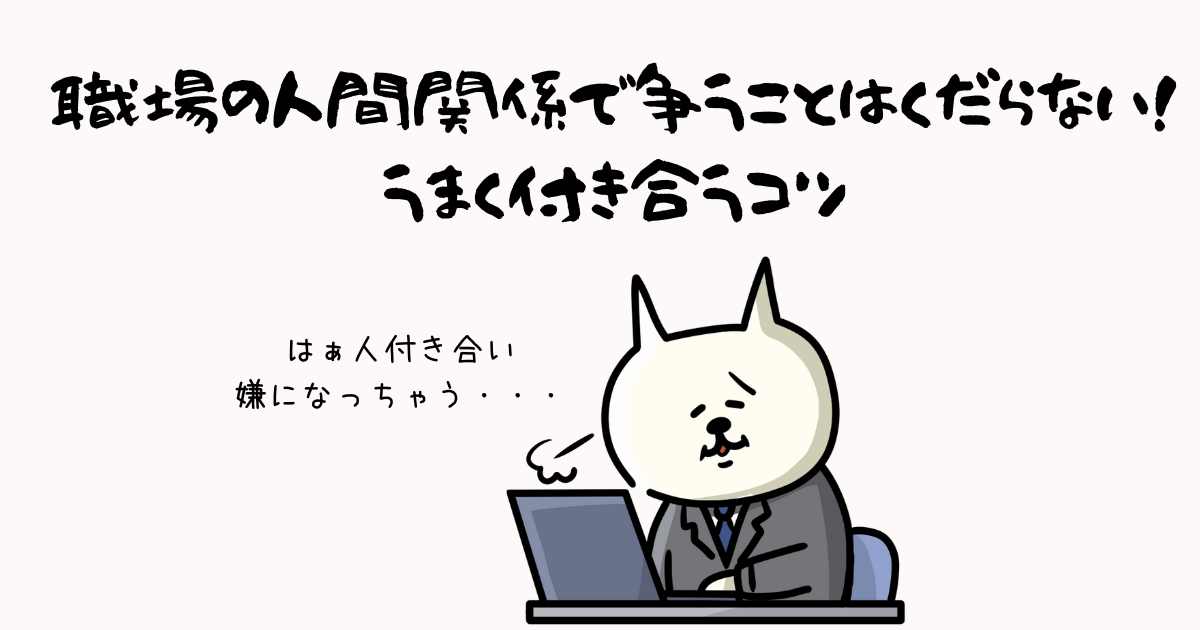
職場の人間関係で争うことはくだらない!うまく付き合うコツ
私たちの仕事に対する人生の割合はどれぐらいでしょうか。8時間睡眠とすれば、起きている時間は16時間であり、一週間で16時間×7日で112時間あります。そのうち8時間は労…
自分の中に一本の芯が生まれる

仕事を“適当に”やっていると、不思議と自分の中に一本の芯が生まれてくる。
それは、自分の努力を最大限に尽くしているからこそ芽生えるものだ。
ただなんとなく仕事をこなしていた頃とは、仕事への向き合い方がまったく変わってくる。
ひとつのことに集中すればするほど、自然と「もっと良くしたい」「もっと成長したい」と思うようになる。
その気持ちは、誰かに教えられて生まれるものではなく、自分の中から湧いてくる。
努力の中で生まれた意欲は、外から与えられるやる気とはまるで質が違う。
仕事のスタイルというのは、他人の真似ではなく、自分の中で最大限努力した結果、にじみ出てくるものだと思う。
人それぞれの人生が違うように、働き方の“型”もまた一人ひとり違っていていい。
私にも、自分なりのこだわりがある。
一人ひとりの患者さんに真剣に向き合う。
妥協してリハビリをしない。
常に「自分ならどう支援できるか」を考え抜く。
そして、日々新しい知識を吸収し続ける。
そうした積み重ねが、自分なりのルールになり、やがて仕事への誇りを生んでくれる。
それは、誰かに認められるための誇りではなく、
「自分は自分の力でここまでやってきた」という静かな確信だ。
常に行動することで悩みをなくせる

何もしていないと、つい色々と考え込んでしまうのが人間だ。
けれど、仕事を黙々と“適当に”やっていると、不思議と仕事に没頭する時間が訪れる。
そのとき、人は余計なことを考えなくなる。
この状態を、禅の言葉で「非思量(ひしりょう)」という。
これは「悩むな、考えるな」という意味ではない。
むしろ、「考えを止めようとしても止まらないのが人間だから、悩みを手放そうとするのではなく、ただ目の前の行為に集中せよ」という教えだ。
つまり、“手を動かす”ことによって、心を静めるという生き方である。
仕事でも同じだ。
言われたことだけを淡々とこなすのではなく、自分に何ができるのか、何をすべきなのかを自分で考えて動く。
思いついたら、できるかどうかを考える前にとにかく試してみる。
うまくいかなければ修正すればいい。
トライ&エラーを重ねるうちに、仕事そのものが自分の思考を研ぎ澄ませてくれる。
人は行動する前に、いつも「やらない理由」を探してしまう。
でも、頭で考えるよりも先に動くことで、ようやく現実が動き始める。
思いついたことを素早く形にする。それが仕事の変化を生み、マンネリを防ぐ。
そして、行動を続けていると、自然と仕事のことしか考えなくなる。
他人への不満や人間関係の悩みが、いつの間にか心の外側に追いやられていく。
それは逃避ではなく、集中の結果として訪れる“静かな境地”だ。
まさにこの状態こそ、「仕事に没頭している」ということ。
考えすぎず、ただ淡々と行う中で、心が澄んでいく。
非思量とは、働くことを通して生きることそのものを整える智慧なのかもしれない。
常に効率化を考えている

“適当な人”は、実は常に仕事の効率化を考えている。
だから、結果的に仕事が早い。
無駄を省き、限られた力をどう使うかを本能的に理解しているのだ。
脳のリソースには限りがある。
人間関係の悩みや余計な不安にそのリソースを使っていれば、当然、仕事に集中するのは難しい。
ましてや効率化なんて、夢のまた夢だ。
大切なのは、仕事に意識を100%向けること。
難しいことではない。
ただ「今日は仕事を適当にやろう」と意識するだけでいい。
“完璧にやろう”と気負わず、ほどよく力を抜くことで、集中力は驚くほど高まる。
そして、仕事が終わったときに自分に問いかけてほしい。
「今日の仕事は100%の力を出し切って、一生懸命やれたか?」
この一言が、自分の中の集中スイッチを育ててくれる。
結局のところ、仕事が進まないのはダラダラしている時間が長いからだ。
サボっているわけではなく、意識が散っているだけ。
だからこそ、意識を一点に向けるだけで、仕事は一気に効率化する。
“適当にやる”というのは、力を抜くことではない。
力を一点に集めるために、余計な力を抜くことだ。
この感覚をつかむだけで、仕事のスピードも、質も、驚くほど変わっていく。
才能にこだわらず上を目指せる

先ほど「才能がない人は夢が叶わないこともある」と話した。
けれど、だからといって努力しなくていい理由にはならない。
むしろ、自分の限界や才能の輪郭を知っている人こそ、本当の意味で努力できる人だと思う。
仕事を“適当に”やる人は、自分の能力を客観的に見ている。
どこまでできて、どこからは無理なのか。
自分のサイズを理解しているからこそ、無理をせずに最大限の努力ができる。
「才能がない=トップにはなれない」――それは事実かもしれない。
でも、だからといって上を目指さないわけではない。
頂点に立てなくても、成長を目指して生きる姿勢は失われない。
私自身、上を目指している自分をどこか誇らしく思う。
結果がどうであれ、上を目指すからこそ仕事が面白くなる。
挑戦する過程で新しい気づきや出会いがあり、自分が少しずつ変わっていくのを感じる。
才能があるかどうかは、自分で決めるものではない。
けれど、努力するかどうかは自分で決められる。
だから私は、自分の才能を言い訳にせず、これからも上を目指し続けたいと思う。
その姿勢こそが、人生を前向きに照らしてくれるからだ。
いまはダメでも、死ぬ気になって何度も何度も挑戦すれば、必ずできるようになります。 しかし、もしも「自分には才能がないから」と思ってしまったら、そこまでです。「このへんでいいや」と思ったときが、終わるときです。成功に価値は無い!
リンク
引用にあるように、私は今はダメでも、死ぬ気でやれば必ずできるようになると信じている。
そして、たとえ未完でもいいと思っているからこそ、努力を続けることができる。
結果だけを追い求めてしまうと、どんな努力もむなしく感じてしまう。
けれど、仕事の過程そのものを楽しめるようになれば、結果なんて二の次でいい。
大切なのは、「できるかどうか」ではなく、「どれだけ夢中でやれたか」だ。
“できないからやらない”というのは、正直、一番かっこ悪い生き方だと思う。
それは自分の可能性を自分で閉ざしてしまう行為だからだ。
できなくても、うまくいかなくても、挑戦し続ける人の姿こそ本当にかっこいい。
最終的にできなくても、何も問題はない。
上を目指し続けるその姿勢こそが、人生を前に進める力になる。
結果がどうであれ、努力している自分を誇りに思えばいい。
私はそうやって、今日も前に進んでいきたい。
明日からあなたも仕事は適当にしよう!

階段を二段、三段飛ばしで駆け上がっていけるのは、才能のある人たちだけだ。
私を含め、ほとんどの人は凡人だと思う。
だからこそ、自分の力量を正しく見極め、その能力の範囲内で地道に仕事を積み重ねていくしかない。
自分の限界がよく分からない人は、まず70〜80%の力でやることを意識してほしい。
なぜ100%ではなく70〜80%なのか。
それは、100%を目指すと必ず心の余裕がなくなるからだ。
焦りと完璧主義が重なれば、せっかくの集中力も持たない。
人の能力は、余白があってこそ最大限に発揮される。
70〜80%の頑張りが、結果的にあなたの力を最も引き出してくれる。
そして、心に余裕がある状態こそが、仕事を長く続けるための土台になる。
たとえ「そこそこの人材」にしかなれなかったとしても、
一生懸命にやってきた自分を自分で認められることが大切だ。
「ここまでやりきった。悔いはない」と思える自負心は、何よりも強い成長の原動力になる。
夏目漱石の言葉にあるように――
「あせってはいけません。ただ、牛のように、図々しく進んでいくのが大事です。」
この言葉は、努力の本質を見事に言い表していると思う。
結果を急がず、粘り強く、図々しいほどに自分を信じて進んでいけばいい。
どんな仕事にも、心の余裕は欠かせない。
余裕があるからこそ人に優しくなれ、発想が生まれ、挑戦を続けられる。
焦らず、慌てず、牛のように一歩ずつ進んでいこう。

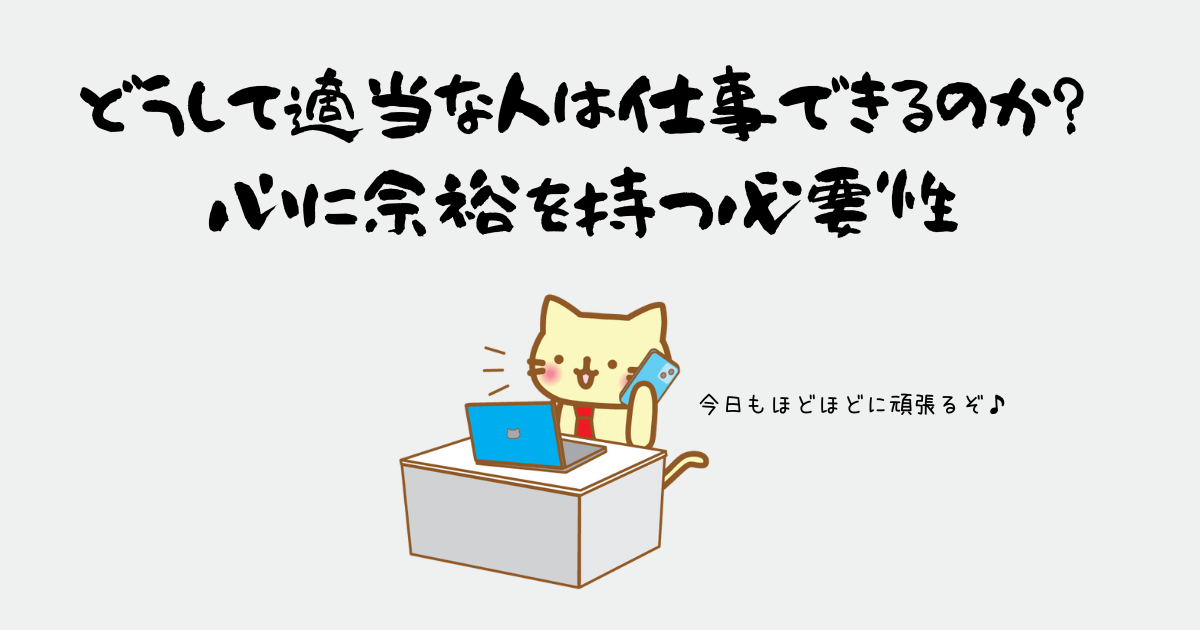

コメント