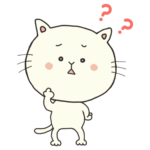 悩みねこ
悩みねこ極限までモノを減らし続けるには何を捨てたらいいですか?
本記事は、極限までモノを減らしたいミニマリストのために、極限までモノを減らし続けた中野善壽さんが捨てたモノを紹介する内容だ。
「極限のミニマリスト」という言葉は私が勝手につけただけで、中野善壽さん本人がミニマリストになろうとしていたわけではない。もともとの生き方が、自然とミニマリスト的だっただけだ。
中野善壽さんは、寺田倉庫株式会社の代表取締役社長、亜東百貨のCOO、株式会社鈴屋の代表取締役専務などを務めてきた人だ。
2021年8月にはACAO SPA & RESORTの代表取締役会長に就任し、今もその道を歩んでいる。
私は中野善壽さんの著書『ぜんぶ、すてれば』に出会うまで、彼のことをまったく知らなかった。
彼の生き方で一番驚いたのは、お金も生活に必要な分以外はすべて寄付していることだ。
ミニマリストは「必要最低限で生きる」ことを大切にしているが、それでも生活の維持だけで精一杯なことが多い。
それに対して中野善壽さんは、稼いだお金までもすべて寄付し、モノだけでなくお金にも執着せずに生きている。
こんな生き方は、普通の人にはなかなか真似できないと思う。
最近はTwitterやYouTubeを見ても、お金の話ばかりで少しうんざりすることが多い。
だからこそ、こういうお金に執着しない生き方を見ると、なんだかホッとする。そう感じるのはきっと私だけじゃないと思う。
ミニマリストというと「モノを捨てる人」という印象が強いが、中野善壽さんはモノ以外のものも手放しており、まさに極限のミニマリストだといえる。
「極限」という言葉は少し大げさかもしれないが、限界ぎりぎりまでモノを減らしている姿を見ると、その呼び方がふさわしいと私は思う。
中野善壽さんの生き方を少しでも参考にすれば、苦しみの原因である「執着」から、少しは自由になれるかもしれない。
執着から解き放たれれば、モノやお金、人間関係に振り回されることも減っていくだろう。
※下の記事でも、モノ以外に「捨てるべきもの」について紹介している。
目次
中野善壽さんの持ち物


どうして中野善壽さんは「極限のミニマリスト」と呼ぶのにふさわしいのだろうか。
その理由は、彼の持ち物がすべて、ハンドキャリーできるほどの小さな鞄ひとつに収まってしまうからだ。
中野善壽 の持ち物
- 下着
- 靴下
- iPad
- 家の鍵
- 眼鏡
- 携帯電話
- 小さな財布
- 薄い手帳
私も自称ミニマリストなのでモノは少ないほうだと思う。
それでも、中野善壽さんのモノの少なさは、あまりにも極端だ。
「服はどうしてるんだろう?」と思うかもしれないが、服は現地で調達している。
社長という立場でありながら、家も車も高級時計も持っていない。
家は台湾にあり、家賃はたったの1万2千円の借家だという。
LOCOTABIの情報によると、台湾の物価は日本の約3分の2らしい。
それを踏まえても、社長という地位を考えれば、家賃1万2千円は安すぎる。
日本で換算すれば、だいたい1万8千円の家に住んでいるようなものだ。
ここまでモノが少なく、家賃まで安いとなると、どれだけ極限のミニマリストなんだろうと思ってしまう。
中野さんに比べたら、私はまだまだひよっこのミニマリストだ。とても真似できそうにない。
家の中がほとんど空っぽで知られるミニマリストのしぶさんでも、全持ち物は219個ある。
それと比べても、中野さんがいかに極限のミニマリストなのかがよく分かる。
極限のミニマリストが捨てたモノ
今日の自分を妨げるものはぜんぶ捨てる


僕が何より伝えたいのは、「今日がすべて」という言葉です。 情報が多く、将来のことも、周りの人も気になる時代において、「今に集中する」のはどんどん難しくなっているのかもしれません。 しかし、事実として、夢中になって楽しむことができるのは今しかありません。ぜんぶ、すてれば
リストラ、円安による物価高、病気、少子高齢化による年金額の減少など、生きているだけで不安になることが多い。
私たちは、今この瞬間に集中するというより、どうしても将来への備えに意識が向いてしまう。
この言葉から学べるのは、「人生の本質は“今”にある」ということだと思う。
現代は、情報があふれていて、誰かの成功や未来の不安がいつでも目に飛び込んでくる。つい、他人と比べて焦ったり、将来の心配ばかりしてしまったりする。でも、そうやって頭の中が“明日”や“誰か”でいっぱいになるほど、“今日”という一日がどんどん遠のいていく。
「今日がすべて」というのは、何も“先を考えるな”という意味じゃない。むしろ、「未来を良くするために、今に集中しよう」というメッセージなんだと思う。人が本気で笑ったり、夢中になって何かをしている時間って、いつも“今”にいる。明日の心配をしているときに心から楽しむことなんてできない。だから、“夢中でいられる今”を積み重ねることこそが、後から振り返ったときに「いい人生だった」と思える一番の近道なんだ。
将来は“今”の延長線上にしかない。未来を変えるためにできることも、過去を癒すためにできることも、すべては“今日”の中にある。だから、「今日がすべて」という言葉は、焦りや不安で曇った心を、もう一度“いま”に戻してくれる。朝の光や食事の味、人との会話、ひとつひとつの瞬間を丁寧に感じ取ること。それが、何よりも確かな生き方なんだと思う。
人付き合いを捨てる
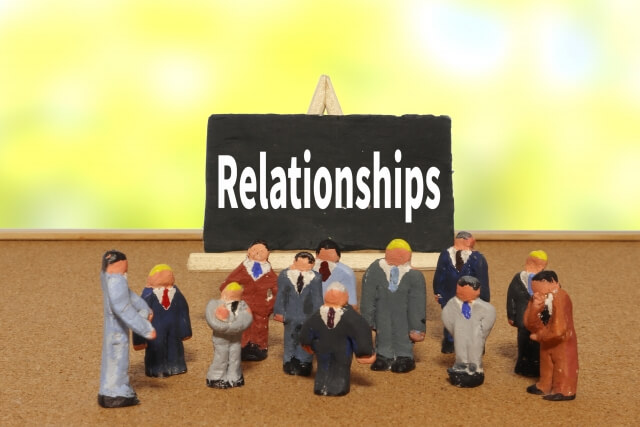
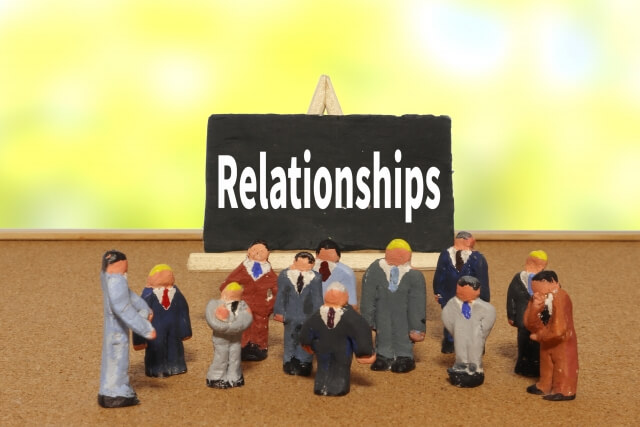
周りと合わせないといけない、という全体主義・同調主義は危険です。 あまりにその圧力が強いと、本当に危険な時に自分の判断で 逃げ出すこともできなくなるし、全員揃って破滅の方向に行くリスクも高くなる。 だから、抵抗心が芽生えたら、それを守り抜くようにしてほしいと思います。ぜんぶ、すてれば
人生には大事な選択肢がいくつもある。
自分で選んでも後悔することはあるけれど、一番後悔するのは、選択を他人に委ねたときだ。
自分が納得していないのだから、後からモヤモヤするのも当然だと思う。
私たちは、子どものころから「協調性が大切」と言われ続けてきたせいで、いつの間にか他人の顔色を伺うのが得意になってしまった。
でも、最近の若い世代は少し違う。
「親ガチャがあるから生まれる環境は選べなくても、ものごころがついてからは自分の意思で人生を選びたい。持って生まれた能力を最大限に活かしたい」という考え方が主流になりつつある。
では、私たちはどうすれば他人とうまく付き合っていけるのだろうか。
付き合いを続けたいのは、明るく未来を語れる仲間。
愚痴や不満を言ってるばかりの人とは、自然と疎遠になります。
ぜんぶ、すてれば
この言葉には、とても共感する。
愚痴を聞くのは気持ちのいいものじゃない。
私は、愚痴や不満ばかり言う人や、自分の価値観を押しつけてくる人とは距離を置いている。
話していても、まったく楽しくないからだ。
私は、たわいもない話でもいいから、明るい話題が好きだ。
他人から有益な情報を得ようとか、付き合うことで得をしようなんて考えて人と関わっていない。
どうでもいい話をしながら笑い合い、心地よい時間を過ごせるだけで、それで十分だと思っている。
人間関係を断捨離して、良いことも悪いこともあった。
それでも、今のほうがずっと生きやすくなったのは確かだ。
私の考えでは、人との関係は「量」ではなく「質」だと思う。
誰と一緒にいるかで、日々の感情の色が変わる。
前を向いている人と話していると、自分まで少し明るくなれる。
逆に、いつも不満ばかり言っている人と過ごすと、知らないうちに心が曇っていく。
だからこそ、明るく未来を語れる人と付き合うことは、自分の心を守る行為でもある。
お互いの明日を少しでも良くしたいと思える関係こそ、本当に大切にしたい人間関係だと思う。
あわせて読みたい




人間関係まで手放さなくていい。ミニマリストがつなぐやさしいつながり
ミニマリストを意識しはじめた頃、私は「持ち物だけじゃなく、人間関係もスッキリさせた方がいいのかな」と思っていました。実際に、無理して出ていた集まりをやめたり…
歳を取れば取るほど、新しく人間関係をつくるのは難しくなる。
けれど、出会いがあれば別れも必ずあるものだ。
最終的には、一人で死んでいかなければならない。
そう考えると、一人で生きていく術を身につけるほうがずっと大切だと思う。
他人に依存することは、自分を失うことにつながる。
だから、人付き合いは他人に依存せず、必要最低限にしておくくらいがちょうどいい。
愛社精神を捨てる


自分はなんのために働くのか。 答えは1つ。自分のため。「会社のため」じゃない。 「家族のため」というのも、ちょっとあやしい。 自分が好きで、楽しいから、目の前の仕事をやっている。 会社というのは、人間が仕事を楽しくするための手段であり、ただの、“箱〟でしかない。ぜんぶ、すてれば
愛社精神を持ったところで、会社が社員を大切にしてくれるわけじゃない。
会社にとって社員のほとんどは、代わりのきく駒でしかない。
私は最初の職場で、自分なりに一生懸命働き、会社に尽くしたつもりだった。
それでも、あっさりと解雇された。
頑張ったところで認めてくれるのは結局自分だけで、会社が同じように評価してくれるとは限らない。
だから私は、会社は自分の能力を買ってくれる場所だと割り切っている。
愛社精神なんていらないし、お互いに依存しない関係が一番いいと思う。
会社は使えないと思えばクビにするし、こちらも「この会社では成長できない」と思えば、迷わず辞めればいい。
お互いにメリットがあるから働く――それがいちばん健全な関係だと私は思っている。
私の考えでは、働く目的を「生活のため」だけにしてしまうと、心がすり減っていく。
仕事は自分の人生を少しでも豊かにするための手段であって、苦しむためのものではない。
だから、自分が納得できる働き方、自分の価値観に合った働き方を選ぶことが大切だと思う。
どんな仕事であっても、「自分がどう生きたいか」という軸があるかどうかで、日々の意味はまったく違ってくる。
会社に自分を合わせるのではなく、自分の人生の中に会社を置く。
それくらいの距離感でいるほうが、心はずっと軽くいられる。
目標を捨てる


始める勇気と同じくらい、大事なのは〝やめる勇気〟。 じゃあ、どうやって〝やめどき〟を見極めるかと聞かれたら、 「がんばり過ぎている」と気づいた時じゃないかと答えます。ぜんぶ、捨てれば
私は運営者情報にも書いたように、医学部再受験をダラダラと5年間も続けてしまった。
どうしてやめられなかったのかというと、単純に“やめる勇気”がなかったからだ。
私にとって医者になることは夢であり、生きがいだった。
それを失ったら、自分が何のために生きているのか分からなくなると思っていた。
医学部再受験の頃は、明らかに頑張りすぎていた。
それでも、自分を見失うことが怖くて、やめる勇気を持てなかった。
若いころは、多少の無理をしても目標に向かってまっすぐ進むことができる。
でも、40代にもなると踏ん張りがきかなくなり、無理をして頑張るのがだんだん難しくなる。
それでも、目標を持つことは歳を重ねても大切だと思う。
目標がないと、どうしても怠惰に、無気力に生きてしまうからだ。
無理をして頑張るのではなく、心に余裕を持った状態で頑張る。
たとえ小さな目標でもいい。挑戦し続けることが、人生に活力を生み出す。
私の考えでは、「やめる勇気」も「続ける勇気」も、どちらも同じくらい大切だと思う。
何かをやめることは、逃げではなく、新しい道を選ぶ行為でもある。
夢をあきらめるのではなく、形を変えて自分の中に残していく――そういう柔軟さこそ、大人になってからの“頑張る”の本当の形なんじゃないかと思う。
夢にしがみつく時期があってもいい。
でも、手放すことで見える景色もある。
そのどちらも、自分の人生を豊かにしてくれる大切な経験なんだと思う。
安定を捨てる


世界の中で必要になるのは、安定を求める心ではなく、変化に対応する力
ぜんぶ、すてれば
2020年に倒産した企業の平均寿命は23.3年らしく、永久に存続する会社なんて存在しない。
自治体ですら、いずれ消える可能性がある。
終身雇用も年功序列も、アメリカのようにいずれなくなるかもしれない。
コロナ禍でいつ会社に首を切られるかもわからない時代だ。
会社は自分を守ってくれない。
実際、私は2021年の8月に会社から解雇された。
職を失ってから、私は「個人で食べていく力」を身につける必要があると強く感じるようになった。
高齢者が増え、出生率が下がり、人口減少が続く日本では、将来年金をもらえるかどうかもわからない。
そんな社会で、収入を断たれることがどれほど不安なことか、身をもって知った。
最近では円安の影響で物価が上がり続け、使えるお金はどんどん減っている。
このように世界は刻々と変化しており、「安定を求める心」だけでは生き残れない。
変化に対応する力を身につけること。
それが、今を生き抜くための現実的な手段だと思う。
古いものにこだわりすぎず、日々の中で新しい技術や価値観に触れていくことが大切だ。
私の考えでは、「変化に対応する力」とは、単に新しいものを追いかけることではなく、「古い価値を手放す勇気」でもある。
安定を求める心は誰の中にもあるが、それに縛られている限り、本当の意味での自由は得られない。
変化とは恐れるものではなく、生きている証のようなものだ。
時代に合わせて自分を少しずつ更新していく。
それこそが、これからの時代に必要な“生きる力”なんだと思う。
モノを捨てる


ものを所有することは安定を生まない。むしろ不安が増えるだけ。 「いつでも移れる。どこでもすぐに新しい生活を始められる」。 人生の選択肢を広げてくれる、そんな軽やかさを持ちたいと僕は思います。ぜんぶ、すてれば
「ものを所有することは安定を生まない。むしろ不安が増えるだけ。
『いつでも移れる。どこでもすぐに新しい生活を始められる』。
人生の選択肢を広げてくれる、そんな軽やかさを持ちたいと僕は思います。」
この言葉に、私はとても共感する。
モノを捨てるという行為は、ミニマリストにとっては当たり前すぎて、今さらだと思うかもしれない。
けれど、なぜそこまでモノを減らしているのか――その理由を、もう一度見つめ直すことは大切だと思う。
私は、車や家、スマホなど高い買い物をするほど、それを失う恐怖が生まれることを知っている。
モノを持てば持つほど、不安は増えていく。
けれど、モノを捨てていくうちに、身軽さが生まれ、人生の選択肢がどんどん広がっていくのを感じる。
たとえば、家を買えば「ここにいつでも戻ってこられる」という安心を得られる一方で、「ここに縛られる」という制約も生まれる。
転職や結婚など、人生のどんなタイミングで環境が変わるかわからない。
だからこそ、私はいつでも動けるように、身軽でいたいと思う。
私の考えでは、モノを減らすことの本質は「自由を取り戻すこと」だと思う。
持たないことは、不安を減らすだけでなく、自分の意志で生きるための力を取り戻す行為でもある。
所有とは、安心を与えるように見えて、実は心を縛る鎖にもなる。
モノを手放すたびに、自分の中の“しがらみ”も少しずつほどけていく。
そうやって身軽になったとき、ようやく「どこでも生きていける」という自由を手に入れられるのだと思う。
予定を捨てる


現場の仕事で忙しい年代だったとしても、 定期的に「何もしない時間」をつくって、 ぼんやりお茶でも飲む習慣を持ってみるのがおすすめです。ぜんぶ、すてれば
私は休日に予定を入れることは絶対にしない。
「何時に〇〇しなければいけない」と思うだけで、強制力を感じてしまい、心も体も休ませることができなくなるからだ。
仕事のときも、ただせっせと働くのではなく、効率化を意識して、同僚と話しながらコーヒーを飲むような“余白の時間”をあえてつくっている。
そうした「何もしない時間」が、私に心の余裕を生み出し、仕事にもメリハリをつけてくれる。
今の時代はSNSなどから絶えず情報が流れ込み、刺激を受け続けている。
そのせいで、暇な時間を悪いことのように感じ、何かをしていなければ落ち着かない人も多い。
けれど、「何かをしなきゃいけない」という思い込みを手放してみると、ようやく心がゆるみ、自分を取り戻すことができる。
私の考えでは、「何もしない時間」は心の栄養だと思う。
忙しさの中でこそ、何も生産しない時間を持つことが、自分を整えるために必要になる。
お茶を飲みながらぼんやり過ごす時間の中で、考えが整理され、次の一歩が自然と見えてくることもある。
現場の仕事で慌ただしい日々の中に、ほんの少しの“間”を持つこと。
それが、長く働き続けるための最大のリフレッシュ方法だと私は思う。
慣れを捨てる


人間は慣れるとバカになる。
頭を使わなくなって、衰えていく。
だから、できるだけ不慣れな機会に身を置くことが大切だと、普段から意識しています。
ぜんぶ、すてれば
人は安心を求める生き物だ。
だから、自分が好きな人とばかり付き合おうとする。
知らない人や苦手な人と話すのはエネルギーを使うし、何より心が落ち着かない。
けれど、新しい人や新しいことに出会って、自分に少し負荷をかけていかないと、世界は広がらない。
やがて同じ毎日が続いて、退屈になってしまう。
落ち着いた生活も大切だけど、生活の中に小さな刺激を入れないと、やる気が失われ、ただ毎日をこなすだけの“生き物”のようになってしまう。
歳を取るほど、新しいことにチャレンジしなくなり、同じルーティンで日々が過ぎていく。
それはとても危ういことだと思う。
私は現在44歳だが、毎日の生活に少しでも変化をつけないと、自分が少しずつ枯れていくのをはっきり感じる。
そうなると、顔から覇気が消え、年齢以上に老けて見える。
見た目と行動力は比例する。
だから、若くありたいなら、新しいことにどんどん挑戦していくことが大切だ。
私の考えでは、「変化を恐れない」というのは、派手なことに挑むという意味ではない。
むしろ、日常の中でほんの少しだけ“未知”を取り入れていくことだと思う。
いつもと違う道を歩いてみる、行ったことのない店に入ってみる、読んだことのない分野の本を開いてみる。
そうした小さな変化の積み重ねが、心の柔軟さを保ち、年齢に負けないエネルギーをつくっていく。
人は安心の中で癒やされ、刺激の中で成長する。
そのどちらもバランスよく持つことが、長く生きるうえでの本当の“若さ”なんだと思う。
あわせて読みたい

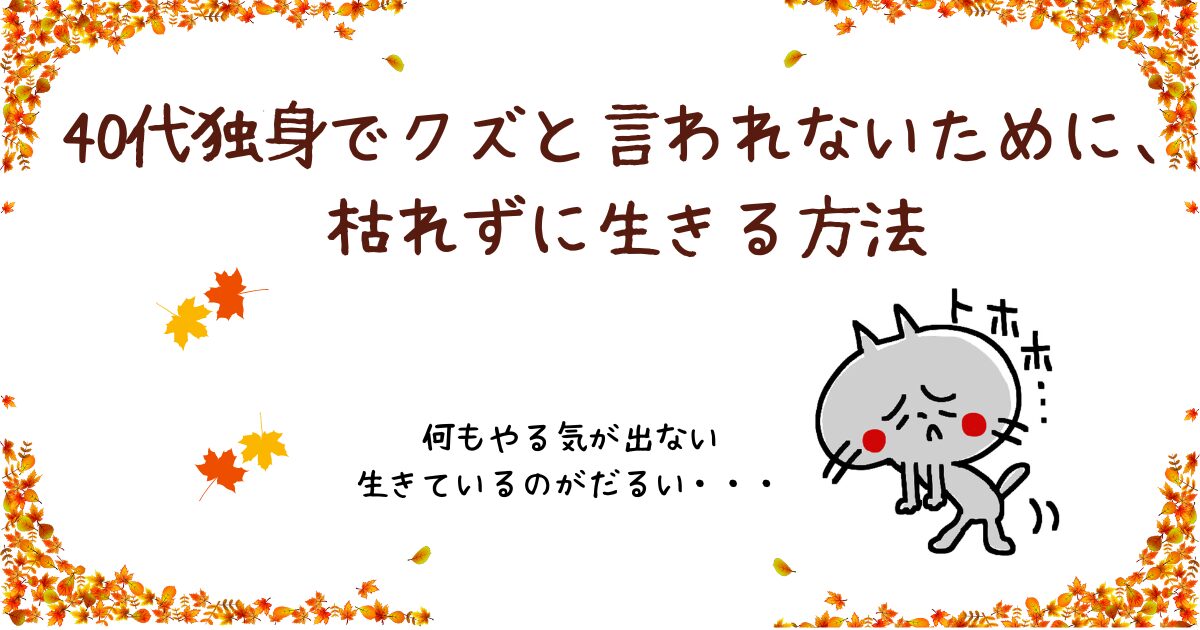
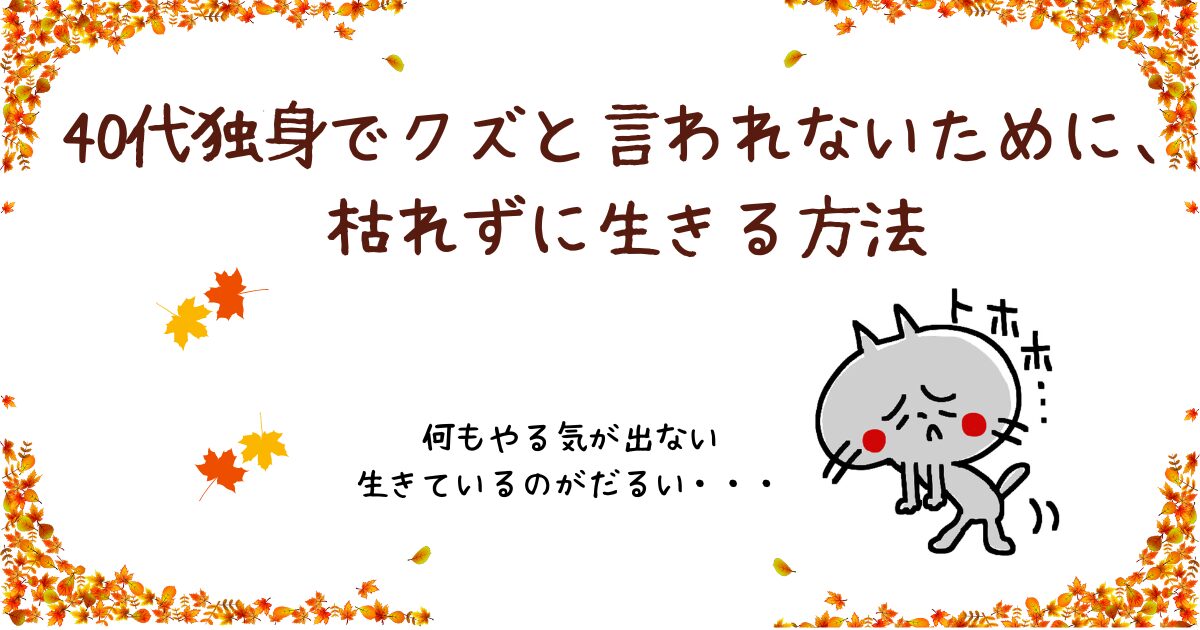
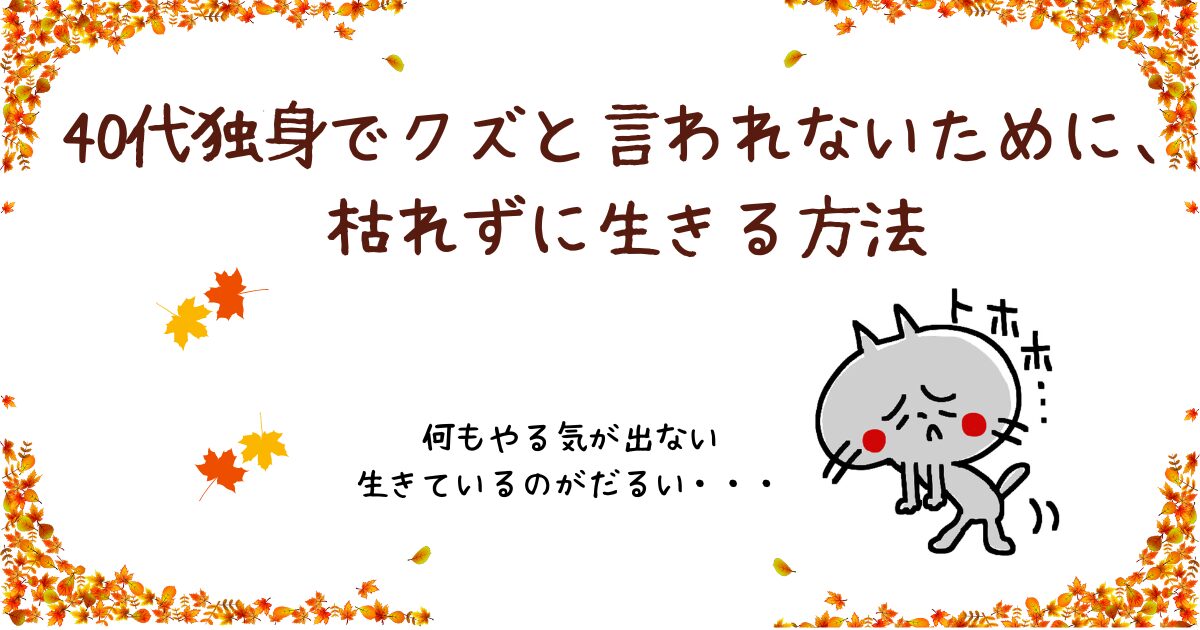
40代独身でクズと言われないために、枯れずに生きる方法
40代で独身ですがクズて言われます。少しはマシに生きる方法はありますか? 本記事は、40代独身でクズだと自覚がある人、言われている人を対象に少しでも枯れずに生きる…
相方への執着を捨てる


僕の夫婦観は、「高め合える関係でなくなったら、離れたほうがお互いのため」。 そのほうが、長い人生をより豊かに、有意義に生きられると思うのです。
ぜんぶ、すてれば
男女間は、とくに依存関係になりやすいと思う。
私もかつてはそうだった。
他人に執着が生まれると、相手がいないと何もできなくなってしまう。
そして、相手との関係がうまくいかないだけで、気になって他のことに集中できなくなる。
中野善壽さんが言うように、お互いに尊敬しあえる関係でないのなら、一緒にいないほうがいいと私も思う。
依存関係では、どちらも幸せにはなれない。
少なくとも私は、当時付き合っていた彼女に依存してしまい、別れるときには泣きじゃくるほど取り乱した。
あの経験を通して、他者に依存することがどれほど怖いものかを身をもって知った。
福沢諭吉の言葉に「独立自尊」がある。
「心身の独立を全うし、自らその身を尊重して人たるの品位を辱めざるもの、これを独立自尊の人という」という意味だが、
goo辞書での説明を借りれば「人に頼らず、自分の力だけで事を行い、自己の人格と尊厳を保つこと」を指す。
少し厳しい言い方かもしれないが、すべての行いは自己責任だという認識がないと、真の意味での独立自尊は成り立たないと思う。
他人に頼らずに生きるのは確かに大変だ。
けれど、だからこそ、私ならそういう覚悟を持った人と一緒にいたいと思う。
私の考えでは、依存しない関係というのは「距離を取る関係」ではなく、「自立した者同士が並んで歩く関係」だと思う。
お互いが自分の軸を持っているからこそ、相手を尊敬できる。
そして、相手に依存しないからこそ、相手の存在を本当に大切にできる。
愛とは支配でも執着でもなく、互いの自由を尊重しあうこと。
それが、本当の意味での“支え合う”関係なんだと思う。
本は捨てる


身軽な自分をキープするには?
そう聞かれたら、とにかく「捨てること」と答えます。
捨てる、捨てる、惜しげもなく、捨てる。
物理的にモノを捨てるのを習慣にしていたら、心も身軽になってきた。
ぜんぶ、すてれば
中野善壽さんは、本を読んだらすぐに捨ててしまうそうだ。
では、もう一度読みたくなったときはどうするのかというと、また新品で買うという。
中野さんにとって、1回目に読んだ自分と、2回目に読みたくなった自分はまったくの別人だ。
だからこそ、本を読むときは“ゼロに戻って”新鮮な気持ちで学びたいらしい。
本を捨てることに対しても、まったく「もったいない」とは思わないようだ。
そう聞くと、「本を捨てる」という行為にもどこか納得してしまう。
私は本を捨てることはできないけれど、最近では紙の本はほとんど買わなくなり、すべてKindleの電子書籍で読むようになった。
紙の本は買ったまま読まないものも多く、何よりかさばる。
ミニマリストを目指す私にとって、紙の本は大きな負担になっていた。
もちろん、紙の本には紙の本の良さがある。
ページをめくる感触や紙の匂い、装丁の美しさ――それらは電子書籍にはない魅力だ。
それでも、身軽に生きることを選ぶなら、紙の本とは距離を置かざるを得ない。
私の考えでは、中野さんが本を捨てるというのは、「学びの姿勢を常に新しく保つ」という生き方の表れだと思う。
知識を“所有”しようとせず、常に新しい自分で受け取り直す。
そこには、モノだけでなく「過去の自分」さえも手放す強さがある。
私も紙の本を手放して電子書籍に移行したとき、どこか心が軽くなった気がした。
モノを減らすことは、単なる整理ではなく、思考を軽くすることでもある。
中野さんのように、学びさえも“新しく出会い直す”という感覚を大切にしていきたい。
服はいつでも捨てる


5年前の服を着ると、5年前の自分に戻っちゃうみたいで好きじゃない。
そもそも、着るものにこだわりすぎると不自由になってしまう、というのが僕の価値観です。
ぜんぶ、すてれば
私の服のチョイスは、無印でシンプルなものを選ぶことが多い。
オシャレは、高い服を買うことではなく、限られた組み合わせの中で楽しむものだと思っている。
私の服のパターンは2〜3種類しかなく、服を選ぶ時間を減らすことで、朝の準備も心もすっきりしている。
「同じ服ばかり着ていると思われたらどうしよう」と考える必要はない。
大切なのは、清潔感があるかどうか、それだけだ。
オシャレを楽しみたい気持ちはあるけれど、服を増やせばその分だけ管理も増える。
だから私は、増やさずに組み合わせで楽しむようにしている。
私の考えでは、服というのは“今の自分”を映す鏡のようなものだ。
古い服を着続けると、知らず知らずのうちに過去の自分の延長線上で生きてしまう。
逆に、今の自分に合った服を選ぶことで、気持ちも前向きになり、思考も軽やかになる。
服にこだわりすぎると不自由になるけれど、何を選ぶかという“意識”は大切だと思う。
服を通して、自分の生き方や価値観が見えてくる。
だから私は、シンプルで、心地よく、今の自分らしくいられる服だけを選びたい。
できないものは捨てる


「仕事は、やりがいを持ってがんばりなさい」という教えをよく聞きます。 それもまた真実。しかし、一方で、「諦めも必要」と僕は思います。 つまり、自分の向き不向きをよく観察して、 「できないものはできない」と諦める力。ぜんぶ、捨てれば
私は人がたくさんいる場所が苦手で、大勢が集まる飲み会などはまず無理だ。
また、大勢の人前で話すことも得意ではないので、できるだけ避けて通るようにしている。
向き不向きを考えるときは、単純に「やりたいか、やりたくないか」で判断すればいいと私は思っている。
誰にでも得意・不得意があるからこそ、仕事の分業が成り立っている。
わざわざ苦手なことを選んで、自分をすり減らす必要はない。
とはいえ、ある程度やってみればできるようになることもある。
だから、極端に嫌なこと以外は、少しだけチャレンジしてみる気持ちも大事だと思う。
長年、自分と付き合っていれば、何が好きで何が嫌いなのか、もうはっきりわかっているはずだ。
「できないものはできない」と認めることは、逃げではなく、自分を守るための知恵だと思う。
私の考えでは、「諦める力」というのは、消極的な言葉に聞こえるけれど、本当はとても前向きな力だ。
人は何かを諦めることで、本当に大切なものを選び取ることができる。
全部をやろうとせず、無理に他人と同じ土俵に立とうとしないこと。
それが、心の平穏を保ちながら、自分らしく生きるためのいちばんの近道だと思う。
定年を捨てる


働き続けるつもりがあれば、「年金がいくら足りない」といった不安もなくなるはず。 年金はご褒美程度のオマケくらいに思わないと。 たくさん稼ぐほどがんばる必要もなくて、 自分ができそうな仕事から始めたらいいんです。ぜんぶ、すてれば
将来に不安を感じるのは、仕事が続けられなくなり、収入を年金に頼らざるを得なくなるからだと思う。
少子高齢化の中で、これまでと同じ金額の年金がもらえるかどうかもわからない。
だから、不安を感じるのは当然のことだ。
けれど、定年を先延ばしして、できる限り働き続けるつもりでいれば、こうした問題の多くは軽減できる。
老化は避けられないが、避けられないからこそ、今の健康を何よりも大切にすべきだと思う。
私は理学療法士として、これまでたくさんの高齢者を見てきた。
その中で感じるのは、介護が必要になる原因は、身体の問題よりも認知症によるものが圧倒的に多いということだ。
認知機能が低下すればするほど、何をしても手遅れになってしまうケースが多い。
頭がクリアであれば、たとえ車椅子になっても十分に働ける。
だからこそ、今から認知症対策を始めることが何よりも重要だ。
私の考えでは、将来の不安を減らす最善の方法は「健康寿命を延ばすこと」だと思う。
貯金や保険も大切だが、健康ほど確実な資産はない。
体を動かし、よく眠り、脳を刺激し、人と関わる。
それを日々の生活に取り入れることが、最も現実的な“老後の備え”になる。
年齢を重ねても、自分の意志で働ける体と頭を保つこと。
それが、これからの時代を不安なく生きるためのいちばんの安心材料だと思う。
どこまでモノを捨てるべきか?


極限までモノを減らしているミニマリストは、中野善壽さんだけでなく、ミニマリストしぶさんなどもいる。
けれど、一般の人が彼らのような生活をそのまま真似するのは、現実的ではないと思う。
モノを減らせば減らすほど、不便さを感じることもあるし、人間である以上、欲しいモノは必ず生まれる。
欲しいモノがあるというのは、仕事をしてお金を稼ぐモチベーションにもなる。
完全に欲を断ち切ってしまえば、何のために働いているのか、わからなくなってしまうだろう。
だからこそ、中野善壽さんの考えを参考にしながらも、自分の中で“要るもの”と“要らないもの”を見極めていくことが大切だと思う。
人間関係の断捨離も同じだ。
歳を取るほど新しい出会いが少なくなることを考えれば、極端に切り捨てるのは得策ではない。
また、生活スタイルを無理に変えて我慢ばかりの暮らしを続けても、人生の楽しみが奪われてしまう。
ミニマリズムを目指すのは、よりよい生活のためであって、不自由を生み出すためではない。
必要なのは、モノを減らすことそのものではなく、モノとの距離感を見つめ直すことだと思う。
ミニマリズムとは“削ること”ではなく、“選ぶこと”だ。
何を持ち、何を持たないかを自分の基準で決める。
その選択の積み重ねが、自分らしい暮らしにつながっていく。
確かに、モノを減らすことで執着が減り、心が軽くなるのは間違いない。
けれど、空っぽの部屋よりも、自分が本当に好きなものに囲まれた小さな空間のほうが、ずっと豊かだと思う。
だから、いきなりすべてを手放す必要はない。
あなたにとって本当に不要なものから、少しずつ減らしていけばいい。
その一歩一歩の中に、心が整っていく感覚がきっと見えてくるはずだ。
最後に:「持たない勇気」が、人生を自由にする


中野善壽さんは、他にも多くのものを捨てている。
彼が物を捨てるときの工夫として、「鞄ひとつだけ」と決めて、その中に入る分だけしか持たないようにしているそうだ。
つまり、自分で「持ち物の枠」を決めることで、自然と数を絞らざるを得ない状況にしている。
最初から「これしか持っていけない」と決めてしまえば、諦めるしかない。
だからこそ、“制限”を設けることが、捨てるための最も効果的な方法なのかもしれない。
「捨てる」という行為は、「いつか使うかもしれない」という“もったいない精神”が働く分だけ、本当に難しい。
所有は執着を生み、その執着にこだわるほど、人は不自由になっていく。
頭ではわかっていても、なかなか手放せないのが人間というものだ。
私もミニマリストとしてモノを減らし、人間関係を整理してから、本当に生きやすくなった。
モノや人との距離を見直すことで、心に余白が生まれ、自分が何を大切にしたいのかがはっきり見えてくる。
自分を知ることは、何を持つか、何を手放すかを知ることでもある。
まずは、「自分は何が好きで、何が嫌いなのか」から見つめ直してみるといい。
それだけでも、暮らしは少しずつ軽くなっていく。
持ち物を減らすのは、空白をつくるためではなく、本当に必要なものが見えるようにするため。
そして、必要なものに囲まれて生きることこそが、豊かさの本質なのだと思う。
中野善壽さんの本を読むと、その言葉の一つひとつが、自分の中の“執着”を見透かしてくるように感じる。
彼の生の声に触れながら、自分にとっての「手放す勇気」について考えてみてほしい。
リンク


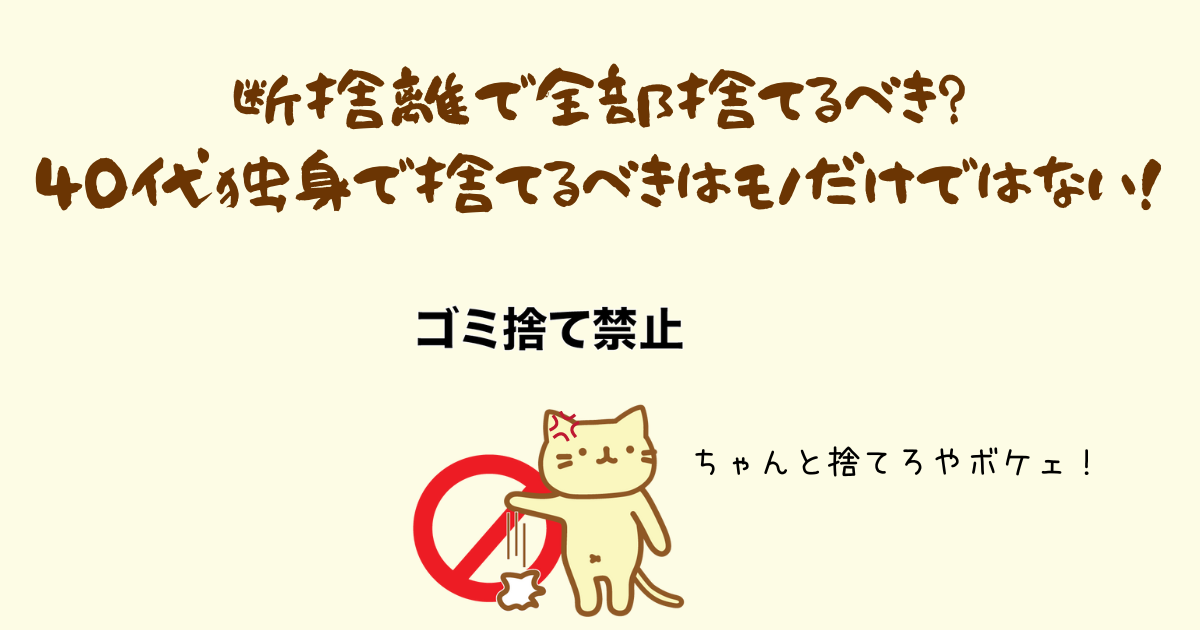

コメント