私は人間関係が苦手です。 40歳にもなると、友達と呼べるほどの友達も少なく、遊べる相手も1,2人程度です。 30歳代の頃は、大学に入学したこともあり、人間関係が一気に増えました。 それでも今でも人間関係が続いているのはごく僅かです。 私の人間関係が続かなかった理由が、鈴木祐さんの『最高の体調 ACTIVE HEALTH』を読んでよく分かりました。 人間関係を親密にするためには『接触時間』『同期行動』『信頼』の3つが必要です。 これらはどれか1つだけあればいいわけではなく、すべてそろってはじめて人間関係が親密になります。 それでは順を追って説明していきます。
リンク
目次
人間関係が続かない理由
人間の脳は人間関係をつくることが苦手
人が人間関係を作りたいと思うのは、孤独感をなくし、幸せだと感じる時間を増やしたいからではないでしょうか。 人が幸せになるためには『オキシトシン』というホルモン(脳内物質)が出る必要があります。 オキシトシンは、リラックス効果や免疫力や細胞修復力を高める効果、痛みの緩和、心臓疾患のリスクを下げる効果など身体の健康にとてもいいホルモンです。 さらに、コレチゾールを下げるストレス解消効果や扁桃体を鎮静させたり、不安を減らしたりする効果があります。 幸せホルモンについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
あわせて読みたい

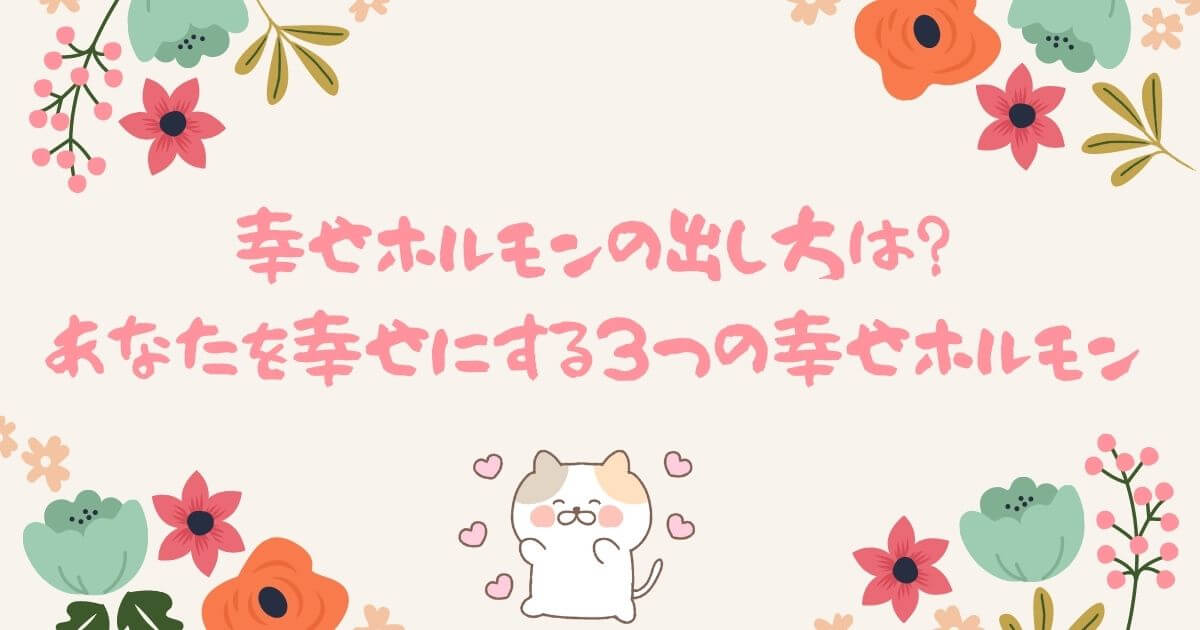
幸せホルモンを増やす方法。あなたを幸せにする3つの幸せホルモン
毎日辛いです・・・。具体的に幸せになる方法を教えて下さい。 こんなお悩みを解決します。 幸せになるためにいい学校に行く、幸せになるために良いところに就職する、…
このホルモンを分泌させるためには、「安定した人間関係」が必要になります。 つまり、人とつながる必要があるわけです。 しかし、私たちの脳は、見知らぬ他人とうまく人間関係を作れるように設計されていません。 理由としては、人類は数百万年前は小さな集団で生きてきたので、家族や近所の人など顔見知りしか存在しませんでした。 このような状況で必要なのは、狭い空間での対人スキルだけです。 しかし、現代では職場での初対面の相手との会話や知らない人だらけの場所に参加したりすることが増えました。 ネットができてからは一気に世界中の人と繋がることができ、外部とのコミュニケーションが加速しました。 私たちは遺伝子上、外向きのコミュニケーションスキルが内臓されていないのに、赤の他人と話さなければならない状況なわけです。
人間関係は、多ければ多いほどよい?
人とのつながりが大切なことは分かりましたが、人間関係は多ければ多いほどいいのでしょうか? オックスフォード大学の調査によれば、この答は「ノー」です。 学生たちの協力を得て彼らの人間関係の変化を18カ月にわたり調査したそうです。 ここで分かったのが、ほとんどの学生が、いつも一定のコミュニケーションサイズを支持し続けているという事実です。 例えばで説明するとある学生が5人の親友がいたとして、社会人になりさらに2人親友が増えたとしても、親友の数が7人になるわけではありません。 前の親友の2人が親友でなくなり、また同じように5人の親友とコミュニケーションを続けるようになります。 このことから、人の認知リソースは大勢の親友とコミュニケーションを取れるようにはできていないため、5人前後としか親密な人間関係を築けません。 社会やSNSでどれだけ友達を作ったとしても、親密に付き合えるのは5人程度ということになります。
同期行動をすると絆が深まる
2016年、オックスフォード大学が「趣味で人間は幸せになれるのか?」という問題について調査しました。 その結果、趣味活動の中でも「合唱」のような他者との関係を結びやすい活動がより人生の満足度、自分に対する肯定感の上昇、炎症レベルの低下といった変化がみられました。 なぜ「合唱」のような集団行動が一番良かった理由は、全員が近い場所にいて、同じタイミングで同じ行動をとっていたからです。これを心理学では「同期行動」といいます。 同期行動を総計200時間をめどに参加していくと、周囲との親密度が格段にアップします。 私は趣味でサイクリングをしていますが、同じようにサイクリングをする友達とは親密な関係を続けられています。 学校で出会った友達でしたが、社会人になってからも会う理由が共通の趣味でしかなかったというのもあります。 飲み会で友人と会っていた時期がありましたが、お金がかかる上、愚痴大会になり気分が嫌になりやすいので飲み会で会う友人とはまったく会わなくなりました。 したがって、趣味活動でも楽しい気持ちいいを同じように共有できるとまた趣味友達と会おうという気分にさせてくれます。
親密な人間関係を続けるためには?
友情を育むためには何が必要でしょうか? 心理学者のロバート・ボーンスタイン氏によるメタ分析では、「特別な刺激がなくても他人と接触する時間を増やすだけで好意は増す」と『接触時間を増やすことが必要』と結論づけています。 しかし、私の体感としては、このメタ分析は、必要条件でもあっても十分条件ではないと思っています。 もし、この条件が当てはまるならば、職場の人間関係で悩む人はいないはずです。 40年生きてきましたが、過ごした時間が長いからといって、友情が生まれたということはありませんでした。 では他に何が必要なのでしょうか? 結論だけ述べれば、友情を育むために必要なモノは「信頼」です。 1度不信感を持ってしまった相手とは、どれだけ長い時間を続けようが友情が生まれたことはありませんでした。 私からしたら、友達という単語をやたら誇示してくる人が一番信頼のおけない人物です。 相手に信頼感を抱かせるためには、心理学的に「自分の悩みや秘密を隠さずに打ち明ける行為」が必要になります。 「私はあたなのことを信頼しているからここまで話せます」というジグナルとして働きます。 しかし、いきなり自分の身の内話を話されても普通は引きます。 そこで、社会心理学者のゲイリー・ウッド氏による研究によると、信頼を得るために話すといい話題は次のことです。
- 自分の夢や目標、希望
- 自分の趣味や興味
- 自分がしてきた中で楽しかったこと
- お金や健康に関する心配事
- 自分が改善したいこと
こういったことを話してもらえれば、確かに一歩距離が縮まったように感じます。 私の中で一番信頼できる人は、『約束を守れる人』と『正直な人』です。 約束を破ったうえに、言い訳をする人がいますが、こういった人は一番信用できません。 世の中は清濁併せ持つものですが、綺麗ごとだけいい、誤魔化す人も信用できません。
根本的に人間関係を作れない人は?
そもそも人間関係を必要としていない、一人が好きという人もいます。 また、人間関係を作ろうと思ってもいつも上手くいかない人も中にはいるわけです。 そんな人達におススメなのが『ペットを飼うこと』です。 犬や猫をなでると飼い主とペットの両方にオキシトシンがでます。 ペットを飼うことは責任を伴いますが、人間関係を築くよりも大分ハードルが下がると思います。 ペットを飼うと自然と顔が緩み、笑顔になります。 笑顔になるだけでドーパミン、エンドルフィン、セロトニン、オキシトシンなどの心と身体を良くする脳内物資が分泌されます。 また、笑顔はコレチゾールのようなストレスホルモンを抑制し、ストレス緩和に働きます。 ペットを飼うという選択肢があってもいいのではないでしょうか。 私は猫を飼っていますが、猫と一緒に寝る時間が最高に至福の時間です。
「悪口」「批判」は脳を傷つける
人間関係を築く上で大切なことは「信用」だと説明しましたが、人間関係を築く上でしてはいけないことは「悪口」です。 多くの人は、悪口は、「ストレス発散」になっていると思っていますが、逆に「悪口」はストレスを増やします。 東フィンランド大学の研究によると、他人に対する批判が多い人は認知症のリスクが3倍、死亡率が1.4倍も高い結果になりました。また、悪口をいうとストレスホルモンであるコレチゾールが分泌されます。 でもどうして悪口をいうと気持ちいいと感じやすいのかというと、ドーパミンも同時に分泌されるからです。 ドーパミンは「楽しい」「幸せ」という感情につながる幸福物質です。 しかし、悪口は、アルコールによってドーパミン分泌を促す「アルコール依存症」と一緒で、「悪口依存症」になっているのです。 「悪口依存症」でドーパミンだけでなく、コレチゾールも分泌も増えるので、徐々に脳や身体をむしばんでいきます。
人間関係を続けるために
コロナ化もあって、人間関係はどんどん希薄化しています。 さらに、歳を取れば取るほど、新しく人間関係を築くことが極端に難しくなります。 このような世の中では、昔ながらの友人を大切にしていかなければいけません。 人間関係を続けるために親密な関係を作るには『接触時間』『同期行動』『信頼』の3つが必要です。 かといって、悪い人間関係もあります。 毎回約束を守らない人、人の悪口ばかり言う人、誠実さに欠ける人です。 こういった人たちとは無理に付き合う必要はありません。 私は人間関係を一部断捨離しましたが、今では本当に良かったと思っています。 何よりストレスがかなり減りました。
あわせて読みたい

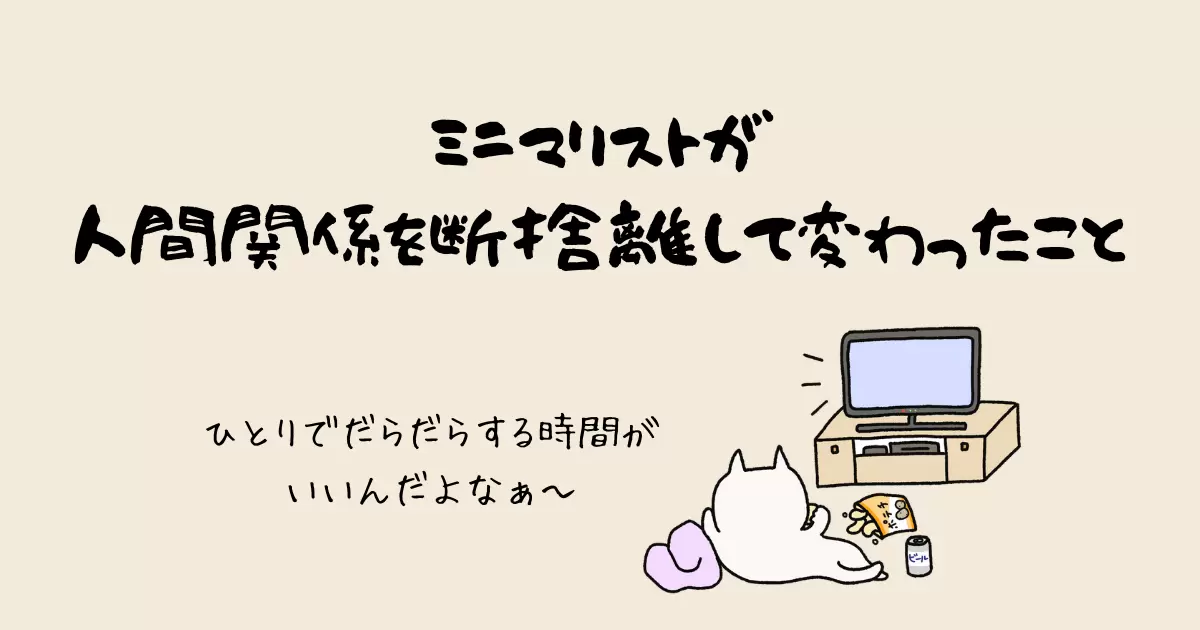
ミニマリストが人間関係を断捨離して変わったこと
ミニマリストが人間関係を断捨離すると生活はどうかわりますか? こんなお悩みを解決します。 私は2021年6月からミニマリストを目指しました。 ミニマリストというとモ…
逆に、信頼をおける人とは長く付き合いたいものです。 ここに書いてあることは、単なるhowtoなのかもしれませんが、頭の片隅に置いておくだけでも人との関係性をうまく保てるようになると思っています。
リンク

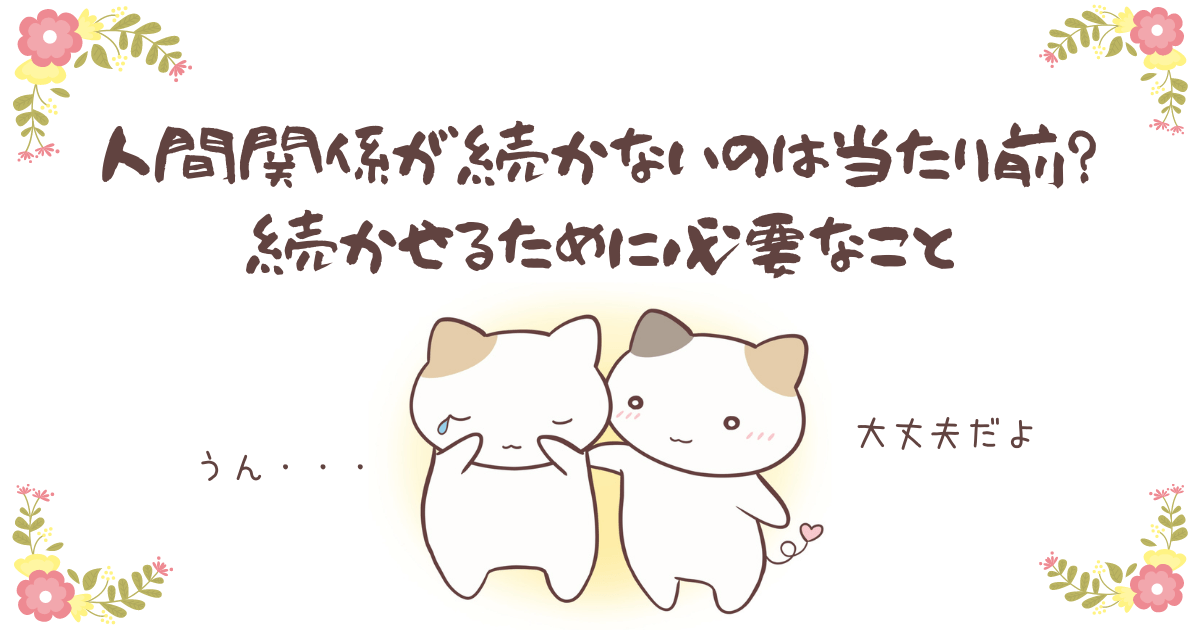



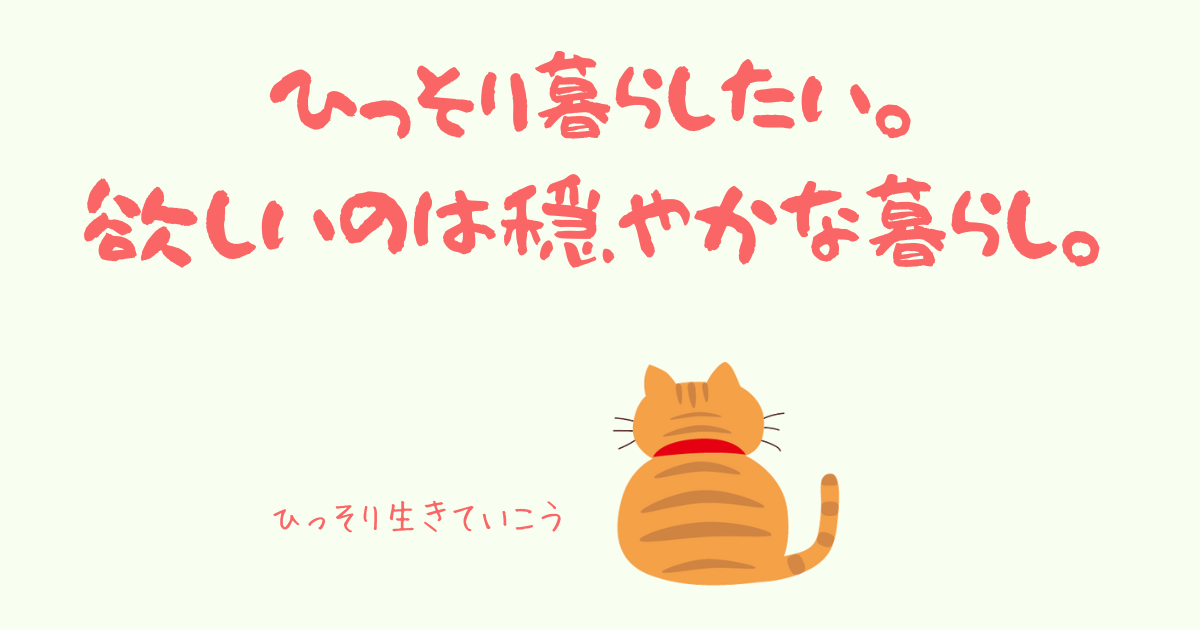
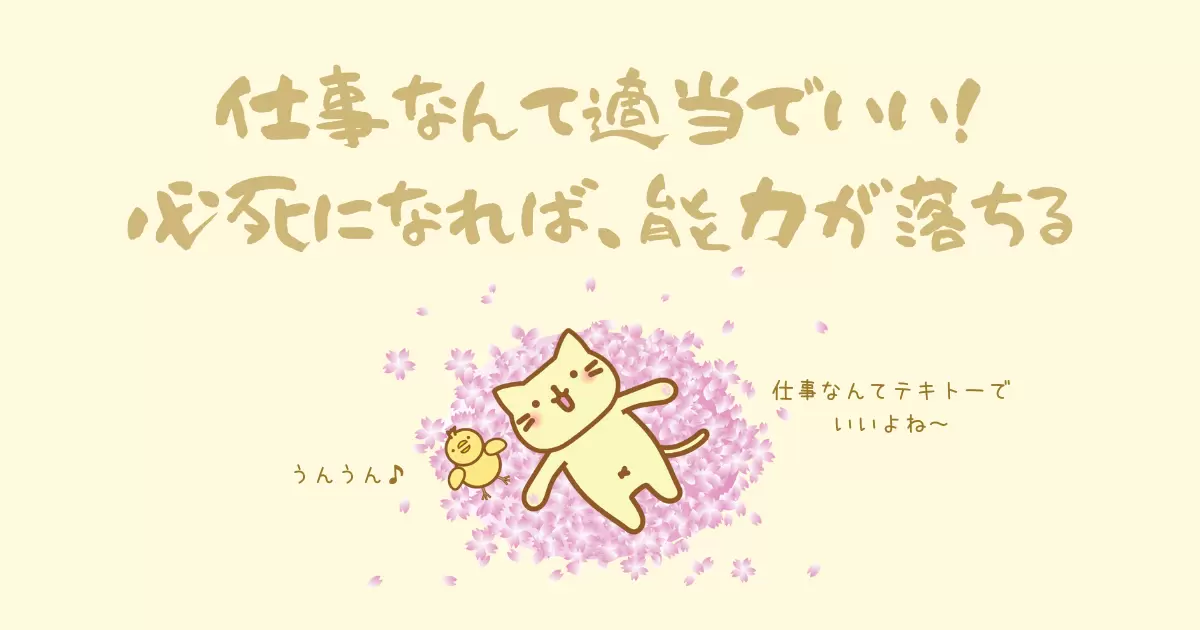
コメント